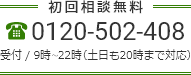オーストラリア訪問記(11)
気がつけば、オーストラリアから帰国して約1か月が経とうとしています・・・。
いつもは、日本への帰国便の機中でこの訪問記をまとめてしまうことが多いのですが、今回はそれが叶わぬ状況でした。
今回、帰国便は、あとでお伝えするアデレードでのセミナー後、最終便でアデレード⇒シドニーに戻り、翌早朝のシドニー⇒羽田を予定しておりましたが、アデレード⇒シドニー最終便が出発1時間前に突然「欠航」になってしまいました(ちなみに、天候は極めて良好・・)。
当然、玉突き的にシドニー⇒羽田便もキャンセルせざるを得ないことに。
憂さ晴らしに、同じ憂き目に遭った税理士の先生と、元々アデレード一泊予定の豪州弁護士の先生とで(今回セミナーで一緒に登壇させていただいた先生方)、夜遅くにラーメンを喰らったのは、せめてもの良い思い出です。
今回は、昨年11月にシドニー&メルボルンで開催した日豪相続セミナーに引き続いて、ゴールドコーストとアデレードの二都市で、以下のセミナーを開催してきました。
▼ゴールドコースト会場▼
日時::2025年4月2日(水) 16:00〜18:00 (現地時間)
場所:Southport Community Centre (6 Lawson Street, Southport QLD 4215)
タイトル:日豪相続セミナー—日豪の相続手続き及び日本の相続税について知っておきたいこと—
▼アデレード会場▼
日時: 2025年4月5日(土) 14:00-15:30 (アデレード時間)
場所: Multicultural Communities Council SA (113 GILBERT ST, ADELAIDE SA)
タイトル:日豪の相続手続き及び 日本の相続税について知っておきたいこと
【主催: The Japan Australia Friendship Association (JAFA/日豪友好協会) 様】
両セミナーのテーマは共通して「日・豪における遺言・相続及び日本の相続税等」で、私は、日本側の法務面の担当スピーカーとして登壇させていただきました。
日本とオーストラリアの間では、今も昔も、日本人の方々の「人」の移動と、それに伴う「資産」の移動が活発に行われており、国境を越えた相続の問題に直面される方が常におられます。
そのような方々においては、両国の法制度や税制が異なる部分も多いため 、戸惑われる方が多く、また手続きも複雑になりがちです。
今回のセミナーでは、こうした状況を踏まえ、日豪間の相続において特に重要となる以下のポイントについて、法務・税務の両面から具体的な解説を行いました。
■適用される法律(準拠法)の判断:
日本とオーストラリア、どちらの法律に基づいて相続手続きを進めるべきか。
■相続手続きの流れと役割分担:
オーストラリアでのProbateの要否や、裁判所・弁護士の関与、日本との手続きの違い。
■遺言書の重要性:
国際相続における遺言書の作成方法、形式、有効性に関する注意点。
■日本の相続税・贈与税:
オーストラリア非居住者であっても日本の税金が課されるケース 、二重国籍の場合の留意点 、課税対象となる財産の範囲 、納税資金対策 、生前贈与など。
両会場とも、オンラインを含めると50名以上の方にご参加いただき、またセミナー後は具体的なご質問も多く寄せられ、本テーマへの関心の高さを改めて認識いたしました。
ご参加いただいた皆様、そして開催にご尽力いただいた共催・主催団体の皆様に、心より感謝申し上げます。
当事務所では、日豪間の相続に関するご相談(オーストラリア側と連携した日本の遺言書作成、遺産分割協議、相続放棄手続サポートなど)を承っております。
また、日本の相続税・贈与税に関するご相談については、国際税務に精通した税理士法人様との連携も可能ですし、豪州現地法に照らした遺言書や信託組成のご相談、さらには実際に相続が開始した後のLetters of AdministrationやProbateなどのオーストラリア法に従った手続に関するご相談について、オーストラリア現地のLaw Firmと連携させていただくことも可能です。
お困りの際はどうぞお気軽にお問い合わせください。

(今回、アデレードに初めてお邪魔しましたが、街並みが大変綺麗で(中心地が綺麗な碁盤の目)、空港からも近く、是非また訪問したい街となりました)
【本内容は、執筆当時の情報をもとに作成しております。また、本コラムは、個別具体的な事案に対する法的アドバイスではなく、あくまで一般的な情報であり、そのため、読者の皆様が当該情報を利用されたことで何らかの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことができません。個別具体的な法的アドバイスを必要とする場合は、必ず専門家(オーストラリア現地法に関する事項は、オーストラリア現地の専門家(弁護士等))に直接ご相談下さい。】
【弁護士 高橋 健/ Lawyer Ken Takahashi】