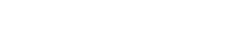プールの瑕疵について
第1 はじめに
季節柄にプール開きも続々と行われてきている中、ファールボール訴訟において大きな論点になっていました施設の瑕疵について、本稿では、「プール施設」に焦点を当てて考えてみたいと思います。
第2 プール施設の瑕疵に関する裁判例(飛び込みにより怪我をした事故関係)
■平成28年4月28日/奈良地方裁判所/民事部/判決/平成26年(ワ)82号
この裁判例は、被告が設置する県立高校のプールにおける飛び込み事故によって傷害を負った原告が、同プールには設置又は管理の瑕疵があったと主張して、国家賠償法2条1項に基づき損害賠償を求めた件につき、同プールは飛び込みを行うのに必要な水深が確保されておらず、通常有すべき安全性を欠いており、設置又は管理の瑕疵があったとしたうえで、原告の過失割合を60%とする過失相殺をしたうえで、請求の一部が認容された事例です。
当該裁判例が「瑕疵」を認定した要素は次のとおりです。
①水深1.00~1.10m未満のプールについて、ガイドライン(日本水泳連盟が定める「プール水深とスタート台の高さに関するガイドライン」)は、安全に配慮された飛び込みスタートを行う場合のスタート台の高さは0.20~0.30mが妥当である。
②ガイドラインは、日本水泳連盟が、全国の既存の水泳プールの現状と競技会・トレーニングの実施状況に照らし合わせ、重篤な飛び込み事故の防止を図るために検討し、平成17年7月6日付けで策定したものであるが、そこで示されている基準は「絶対的な安全基準」という性格ではなく、現実的な妥協点ともいうべきものであって、ガイドラインどおりの設定で実施した飛び込みのスタートであっても、陸上・水中での姿勢・動作等の要因が複合すれば、プール底に頭を強打して飛び込み事故が起こることは想定されており、必ずしも十分な水深がないプール施設での事故発生の危険性を、適切・合理的なスタート方法によって回避できることを前提としているものである。
③ガイドラインが示す基準は、スタート台の高さに関するものではあるが、飛び込みの際の事故発生の危険性を考察する観点からは、飛び込み地点の水面上の高さが問題となるのであって、それがスタート台の高さであるか端壁上部の立ち上がりの高さであるかを区別する意味はない。
④そうすると、ガイドラインは、飛び込み事故の発生を防止するための最低限度の基準として、水深1.00~1.10m未満のプールにおいては、水面上の高さが0.30mを超える地点からの飛び込みを行わせるべきではない旨を定めたものと解され、これに適合しないプールは、飛び込みを行って使用するプールとしては、通常有すべき安全性を欠くものと推認するのが相当である。
⑤本件事故当時、本件プールの水深は、長辺の両端壁から1m地点において、設計上の水深(1.2m)を0.14m下回る1.06mであり、その水面から端壁上部までの立ち上がりは0.37mであったから、本件プールはガイドラインの要求する水深が確保できておらず、スタート台のみならず端壁上部からの飛び込みを行わせるべきではない客観的状態にあったものと認められる。
■平成24年10月4日/名古屋高等裁判所/民事第3部/判決/平成24年(ネ)316号
この裁判例は、中学3年生の男子が、私営の流水プールで逆飛び込み(※頭からの飛び込み)をして頸髄損傷等の傷害を負った事故において、本件プールについては、これに逆飛び込みをした場合には、頚髄損傷等の重篤な人身事故が発生するという危険があるが、プール管理者により本件プールにおける飛び込みが一律に禁止され、その旨が明示されていたのであるから、警告板を見て本件プールにおける飛び込みが禁止されていることを理解し、これに従って行動ができるだけの思慮分別を備えた利用者である本件男子との関係では、本件プールについて本件危険があることをもって、本件プールが通常備えるべき安全性に欠けるものということはできないとされた事例です。
当該裁判例が「瑕疵」を否定した要素は次のとおりです。
①本件プールの構造・形状及び利用状況などによると、本件プールは、レジャー用プールであって、競泳競技用のプールでなく、競泳競技において行われる逆飛込みを予定した設備構造となっていないことは、その外形などからも明らか。
②本件プールにおける飛込みを一律に禁止し、周囲の壁等にその旨の警告板を設置してそのことを明示しているのであるから、本件プールについて、少なくとも逆飛込みする方法でこれを利用することは、本件プールの本来の用法ということはできない。
③本件プールについては、平成7年2月の開業以来、本件事故発生までの約13年半にわたって、飛込みによる人身事故は発生していない。
④本件プールについて、飛込禁止措置にもかかわらず、飛込みが頻繁に、あるいはしばしば行われるなどにより飛込禁止が有名無実と化しているというような事実も認められない。
⑤本件プールにおける逆飛込みが本件プールの通常の用法であるということもできない。
⑥本件プールについては、これに逆飛込みをした場合には、頚髄損傷等の重篤な人身事故が発生するという本件危険があるのであるが、上記のとおり、被控訴人により本件プールにおける飛込みが一律に禁止され、その旨が警告板によって明示されているのであるから、本件プールの利用者が飛込みを禁止する警告板に従って逆飛込みをするようなことはないものと期待できるし、社会通念上そのように期待することは相当であるので、本件プールについて本件危険があることをもって、本件プールが通常備えるべき安全性に欠けるものということはできない。
第3 ポイント
「瑕疵」の判断において、名古屋高裁の事例において「瑕疵」が否定された理由は、利用者が飛込みを禁止する警告板に従って逆飛込みをするようなことはないものと期待できるし、社会通念上そのように期待することは相当であったことが大きなポイントとなっています。
一方で、「本件プールでの飛込みを禁止していることを利用者に周知させるための措置(例えば、館内放送でその旨を放送する措置やプールの周囲に柵を設置するなどして飛込みを困難とするような設備を設置する等の措置)は講じられていなかったのであるから、飛込禁止の警告板の記載を理解できない者やそれに従って行動することが必ずしも期待できない者(幼児や小学生など)との関係で、本件プールについて上記の安全性が十分に確保されているといえるか否かについては、上記のような幼児や小学生については、同伴する保護者において、飛込禁止の警告板の趣旨を十分に説明するとともに、飛込行為をしないように適宜行動を監視し、注意を与えるなどのことが期待されるところではあるが、なお疑問がないわけではない。」とも判示されており、被害者の属性によっては、「瑕疵」が認定される余地があったことが示唆されています。
このように、「瑕疵」が被害者の属性によって変わりうるという点に関して、奈良地裁の事例では、被告は、「本件事故は原告が約1.1~1.2m先に水面に垂直に近い角度で飛び込むなどという通常では想定し得ない飛び込み方法によって発生した自損事故であって、ガイドラインの要求する水深の差が事故発生に影響を与えたものではないから、本件プールに管理上の瑕疵があったということはできない旨主張」している。
当該主張も、「瑕疵」の結論が被害者の属性や行動によって変わりうることを前提とした主張のように思われ、この点について裁判所も「仮に被告が主張するような危険な態様で原告が飛び込みを行ったものであるとしても、原告が友人と悪ふざけをするなどして意図的にそのような態様の飛び込みを行ったものと認めるに足りる証拠はなく、かえって、証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告は、普通の飛び込みを意図しながらも、蹴りの力が弱いなどといった通常生じ得るようなミスにより、本件プールの底面に対して垂直に近い角度で入水し、底面に頭部を衝突させたものと推認される。そうである以上、本件事故が通常では想定し得ない飛び込み方法によって発生したものということはできず、結局、本件プールは、飛び込みを行って使用するプールとして通常有すべき安全性を欠いたものであり、設置又は管理の瑕疵があったものというべきである」と判示し、意図的に通常では想定し得ない飛び込み方法によって発生させた場合には、当該行為との関係では「瑕疵」を否定する可能性、すなわち「瑕疵」の結論が被害者の属性や行動によって変わりうることを示唆しています。
ただ、続いて、「なお、本件事故が原告の自損事故である旨の被告の主張は、本件プールの瑕疵との間の因果関係を争う趣旨とも解されるが、上記に説示したところによれば、本件事故が通常想定し得る範囲内のものであって、本件プールの瑕疵との間に因果関係があることは明らかであるから、被告の上記主張は採用することができない。ただし、原告の上記ミスについては、過失相殺の対象とすべきである。」と判示し、被害者の行為態様については、「瑕疵」そのものとは別に、「瑕疵」と損害との因果関係の問題として整理することも示されているところです。
「瑕疵」の判断において、「営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含」む(■昭和56年12月16日/最高裁判所大法廷/判決/昭和51年(オ)395号:コラム「施設管理者の責任について」参照)という最高裁判例があるため、「瑕疵」の判断において「供用目的に沿って利用されること」についてはもちろん十分に意識をする必要があるものの、被害者の属性や行動を、「供用目的に沿って利用されること」との関連で、どのような場合に「瑕疵」そのものの判断に組み込むのかという点は、結論を左右する重大なポイントになるものと思われます。
事故が発生する以上、何らかの想定し得ない事情が含まれていることが多いものの、その中から、いかに通常の利用態様とそうではない態様を分けるかが勝負の分かれ目になるものと認識し、対応することが必要になるのではないでしょうか。
以上
(弁護士 武田雄司)