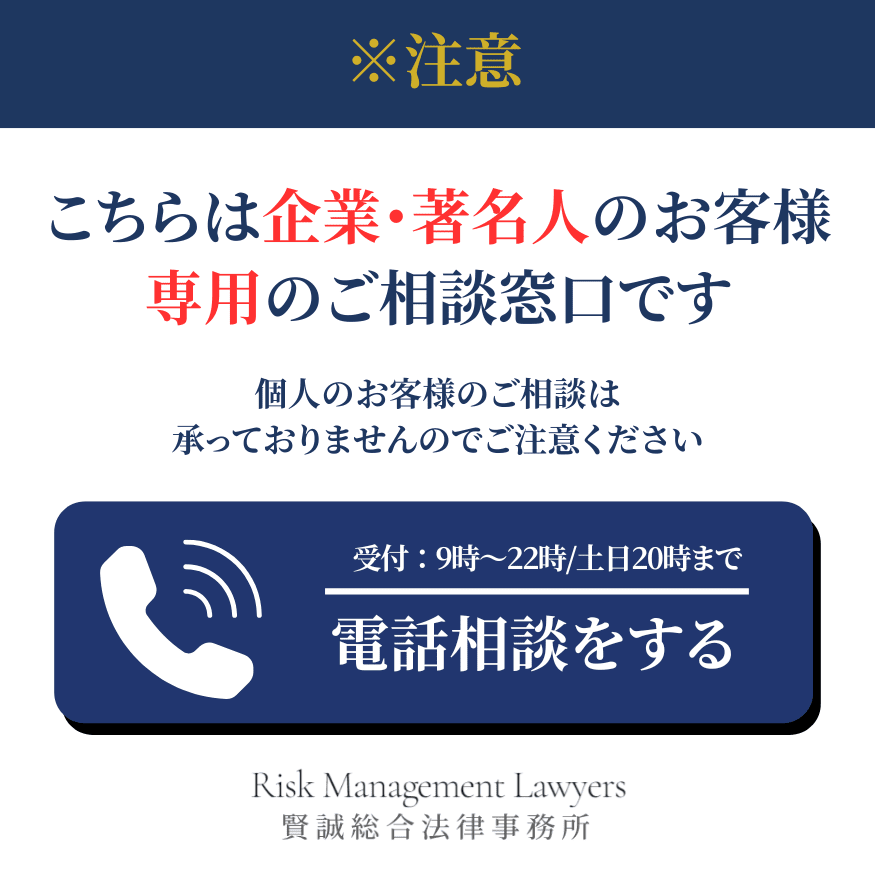不正調査における関連資料の分析
1 不正調査における関連資料の分析
企業におけ不正調査に当たっては、企業に関わる資料の分析が不可欠です。
本コラムでは
①卸売会社の従業員が、会社の在庫商品を勝手に小売業者に販売し、その売上をすべて自分のものにしていたケース
②卸売会社の従業員が、小売業者に対し本来の販売価格よりも上乗せした金額で商品を販売し、会社には本来の販売価格のみを入金し、上乗せ分を自分のものにしていたケース
について、企業の関連資料にそれがどのように現れることになるのかをご説明します。
2 ① のケースについて
まず、この場合は、卸売会社が売主となって販売する場合に、当然卸売会社が作成することになる見積書、売買契約書、注文請書等が存在しないことになります。
また、小売業者から卸売会社に通常送付されるはずの注文書や発注書も、卸売会社には存在しないことになります。
他方、このようなケースでは、棚卸時の会社の商品の在庫の数と売上が全く合わなくなってきますので、棚卸時に在庫の数と売上が合わないことが継続したり、その差が拡大していくような場合には、在庫を確認する回数を増やしたり、商品ごとにこまめに売上を記録していくという対策が必要となります。
また、このようなケースでは、販売先の小売業者が判明している場合には、当該小売業者が卸売会社に対して協力的であれば、これまでの注文書や発注書を再発行してもらい、その発行先が誰になっているか(卸売会社なのか、従業員個人なのか、あるいは、それ以外の第三者なのか)を確認し、それに対応する売上が卸売会社において計上されているかということを売上データを参照して確認することになります。
このような資料の分析を踏まえ、従業員が会社の在庫を勝手に販売し、売上を自分のものにしている疑いが強まった場合には、当該従業員に対する懲戒処分、損害賠償請求及び刑事告訴を検討することになります。
3 ②のケースについて
この場合は、当該従業員が卸売会社の取引として、在庫商品を小売業者に販売しているので、データ上の在庫と実在庫にずれはないことになります。
ただ、卸売会社に保管されることになる注文書、注文請書、売買契約書及び見積書の金額が、上乗せされた金額のままでは、売上の額と整合しなくなってしまうので、多くの場合、上乗せしていない本来の販売価格での注文書等が卸売会社には保管されているはずです。
しかし、小売業者には、上乗せした金額を支払ってもらう必要があるため、当該従業員は、小売業者に対しては、上乗せした金額の見積書、注文請書等を発行しているはずです。つまり、卸売会社に保管されている見積書等と氷業者に保管されている。見積もり書等の金額が一致しなくなるため、当該小売業者が卸売会社に対して協力的であれば、これまでの注文書や発注書を再発行してもらうことによって、当該従業員が上乗せ分を自分のものにしていたことが発覚することになります。
以上のとおり、企業の関連資料を相互に照らし合わせることにより、不正の兆候を発見できる可能性があるため、定期的に企業の関連資料を見返し、数字や表記におかしなところがないかを確認することをおすすめします。
(弁護士|公認不正検査士 伊藤亮二)