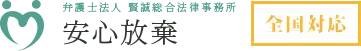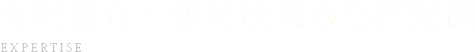兄弟姉妹の相続放棄は一人だけでも可能!兄弟への影響と注意点を解説
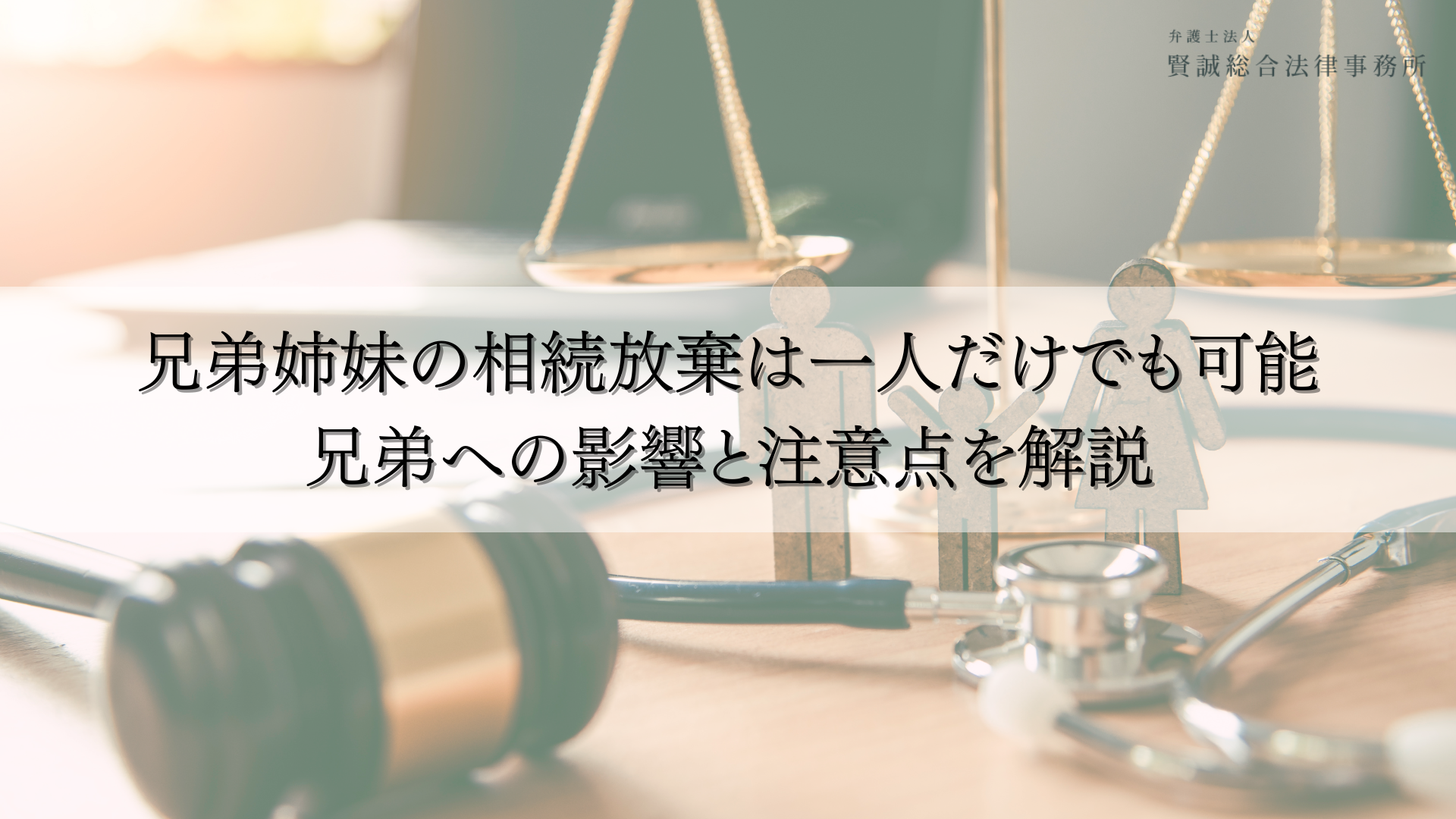
相続放棄の悩み
実績豊富な専門弁護士に
お任せしませんか?
- 6.6 万円/1人 ※追加費用無し
- 解決実績 2,500 件以上
-
全国対応
来所不要
「相続放棄したいけど、自分だけ放棄しても大丈夫?」
「兄弟に迷惑をかけたり、トラブルになったりしない?」
そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、兄弟姉妹の中で自分一人だけが相続放棄することは法律上可能です。しかし、放棄によって他の兄弟姉妹に相続分が集中したり、借金や不動産の管理負担が移ったりと、予期せぬ影響が生じることがあります。
本記事では以下について、法律の専門的視点を交えながらわかりやすく解説します。
- 兄弟姉妹の中で一人だけ相続放棄する方法と条件
- 放棄による相続分や具体的なトラブルの内容
- 兄弟間で円満に放棄を進めるための注意点
- 相続放棄後に残る可能性のある責任(管理義務など)
「相続を放棄したいけど、後悔したくない」そんな方に向けて、安心して判断できるための知識をお届けします。
1、兄弟姉妹の中で一人だけ相続放棄することは可能
相続放棄は、相続人それぞれが自分の意思で判断し、個別に手続きできる制度です。兄弟姉妹の中で一人だけが放棄することも、法律上は問題ありません。
たとえば、兄弟3人のうち自分だけが「借金を相続したくない」「他の兄弟に任せたい」と考えて放棄することも可能です。ただし、相続放棄には明確なルールと期限があるため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。
(1)相続放棄は他人の同意なく単独で行える
相続放棄は、相続人が家庭裁判所に申述するだけで成立します。他の兄弟姉妹の同意や連名での手続きは不要で、自分一人で手続きを進めることができます。
(2)相続放棄が有効になるための2つの条件
相続放棄が正式に認められるには、次の条件をすべて満たす必要があります。
① 相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きする
相続放棄には「熟慮期間」と呼ばれる期限があり、原則として被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に手続しなければなりません。
よく誤解される点ですが、被相続人の死亡日が起算日になるわけではありませんので、たとえば、疎遠だった兄の死を1ヶ月後に知った場合は、「その事実を知った日」から3ヶ月間がカウントされます。
② 家庭裁判所に申述書を提出する
申述書は、相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ郵送または持参で提出します。遺産があってもなくても、この手続きは必須です。
相続放棄の不安、弁護士に丸ごとお任せしませんか?
初回相談無料/一律6.6万円(税込)※実費・債権者対応込み/全国対応・来所不要/実績2,500件以上。弁護士が完了まで代理対応、最短即日で催促ストップも可能です。
- 借金・滞納の請求が届いている/連絡を止めたい
- 3か月の期限が迫っている/過ぎてしまったかもしれない
- 書類作成や戸籍収集など手続きが不安・時間がない
- 家族全員で放棄したい/次順位の相続人への波及が心配
このようなお困りごとは、相続放棄に強い弁護士におまかせください。
2、兄弟姉妹が一人だけ相続放棄をした場合の影響
兄弟姉妹の中で一人だけが相続放棄を行うと、その法的・金銭的・心理的な影響は、他の兄弟姉妹に大きくのしかかります。
「自分だけは放棄したから安心」と思っていても、放棄後の周囲の変化により、後悔やトラブルが発生することも少なくありません。
ここでは、一人だけの相続放棄が他の兄弟姉妹に与える主な影響について、具体的に解説します。
(1)他の兄弟姉妹の相続分が増える
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったとみなされます。結果として、他の法定相続人の相続分が増えることになります。
たとえば、以下のようなケースを考えてみましょう。
- 被相続人に兄弟姉妹が3人いた場合、法定相続分は1/3ずつ
- このうち1人が相続放棄をすると、残りの2人で均等に分けることになる
- 結果として、1/2ずつ(=50%ずつ)の相続となる
一見すると相続額が増えるように見えますが、注意すべき点があります。
- 遺産の中に借金や滞納税金、不動産の管理責任が含まれていた場合、負債や義務の負担も増加
- 空き家や老朽化物件を相続することになれば、修繕費・固定資産税・維持管理費などの負担がある
つまり、一人だけが相続放棄をすると、他の兄弟姉妹に資産だけでなく負債も多く引き継がせてしまう恐れがあります。
(2)相続トラブルが起こる可能性がある
一人だけの相続放棄は、他の兄弟姉妹との感情的な摩擦や法的な争いの火種になることもあります。
特に次のような状況では、放棄がトラブルを招くことが多くあります。
- 放棄した人が他の相続人に連絡しないまま手続きを完了させた
- 後から知った兄弟が「自分だけ不利な立場にされた」と感じた
- 借金や管理義務のある財産を押し付けられたように見えた
こうした誤解や不信感は、兄弟姉妹間の関係性を損なう大きな原因になります。
3、兄弟姉妹で相続放棄をする際の注意点
兄弟姉妹の中で誰かが相続放棄を行うと、残された人たちの相続分や負担に影響を与えることがあります。円滑に放棄を進め、関係悪化を防ぐためには、法的手続だけでなく、家族間のコミュニケーションを丁寧に行うことが重要です。
ここでは、実際に放棄する際に気をつけるべきポイントを具体的に解説します。
(1)相続放棄をしたことを他の兄弟姉妹に伝える
相続放棄は、個人の手続きで完了するため、他の兄弟姉妹に通知する義務は法律上ありません。しかし、放棄したことを誰にも伝えずに進めてしまうと、次のようなトラブルにつながることがあります。
- 他の兄弟が相続人となったことに気づかず、借金の請求が突然届く
- 「勝手に放棄された」「責任を押し付けられた」と感じ、人間関係が悪化する
特に、被相続人に負債がある場合は、放棄によって借金の返済義務が他の兄弟姉妹に移ることもあるため、事前にしっかり説明しておくことが非常に重要です。
(2)必要であれば相続放棄の手続きを兄弟姉妹まとめて行う
相続財産に借金や空き家、不要な土地など処分が困難なものが含まれている場合、兄弟姉妹全員での相続放棄を検討するのが合理的です。
- 一部の人だけが放棄すると、残った人にすべての負担が集中してしまう
- 同じタイミングで放棄することで、家族間の不公平感や誤解を防止できる
また、この場合、裁判所に提出する戸籍謄本等の準備もまとめて揃えることができるため、スムーズに手続きを進めることができます。
(3)不動産は相続放棄をしても保存義務が残る可能性がある
相続放棄をしたからといって、すべての責任から解放されるとは限りません。
特に、空き家や土地などの不動産がある場合、「放棄した人が実際にその不動産を使っていた・管理していた」と見なされると、一定の保存義務を負う可能性があります。
具体的には以下のようなケースです。
- 被相続人が住んでいた家を定期的に管理していた → 管理を怠った結果、雨漏りや崩壊で近隣に損害を与えた場合、損害賠償責任が発生する可能性がある
相続放棄の不安、弁護士に丸ごとお任せしませんか?
初回相談無料/一律6.6万円(税込)※実費・債権者対応込み/全国対応・来所不要/実績2,500件以上。弁護士が完了まで代理対応、最短即日で催促ストップも可能です。
4、兄弟姉妹の相続放棄に関するQ&A
相続放棄について、兄弟姉妹間でよく寄せられる質問にお答えします。
(1)全員が相続放棄した場合はどうなる?
相続人全員が相続放棄をすると、相続人が誰もいない状態になります。その後、利害関係人等による申立てにより、「相続財産管理人」が選任され、最終的には国のものになります。
相続放棄の相談は賢誠総合法律事務所へ
当事務所は、全国から多数の相続放棄の依頼を受けており、確かな実績を有しております。
熟慮期間を経過していたり、他の事務所で難しいと言われたりした場合でも、是非一度ご相談頂ければと存じます。
必要戸籍一式の取り寄せから、各案件に応じた申述書の作成、裁判所とのやり取り、最終的な受理まで、全て代理人である弁護士にお任せいただけます。また、被相続人の債権者への相続放棄の通知対応も致しますので、ご依頼者様の精神的なご負担も大幅に軽減されることと思います。
費用につきましては、全ての実費込みで、お一人当たり一律6万6000円(税込み)です。追加費用は頂きませんので、安心してご依頼頂けます。
相続放棄は是非、賢誠総合法律事務所にご相談ください。
まとめ
兄弟姉妹の中で一人だけ相続放棄をすることは法律上可能ですが、その進め方には慎重さが求められます。相続放棄は単独で手続きできる一方で、放棄したことによって他の兄弟姉妹に相続分や負債が移るなど、想像以上に大きな影響が及ぶからです。
特に注意すべきポイントは以下の3つです。
- 3ヶ月以内という期限内に、家庭裁判所で正式な申述手続きが必要
- 放棄後は、他の兄弟姉妹に通知しなければトラブルに発展するリスクがある
- 不動産などを「管理していた」場合、放棄しても保存義務を問われる可能性がある
つまり、相続放棄は「放棄すれば終わり」ではないケースも存在します。法律的にも人間関係的にも、全体のバランスと影響を見通した対応が求められる行為です。
判断に迷ったときや、相続財産に不動産・借金・空き家が含まれている場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 一人で悩まず、専門家と一緒に「納得のいく相続対応」を選びましょう。
2025.07.16野田俊之
相続放棄の悩み
実績豊富な専門弁護士に
お任せしませんか?
- 6.6 万円/1人 ※追加費用無し
- 解決実績 2,500 件以上
-
全国対応
来所不要