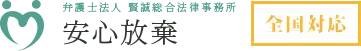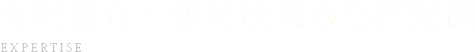相続放棄での兄弟姉妹トラブルの事例は?回避する方法についても解説
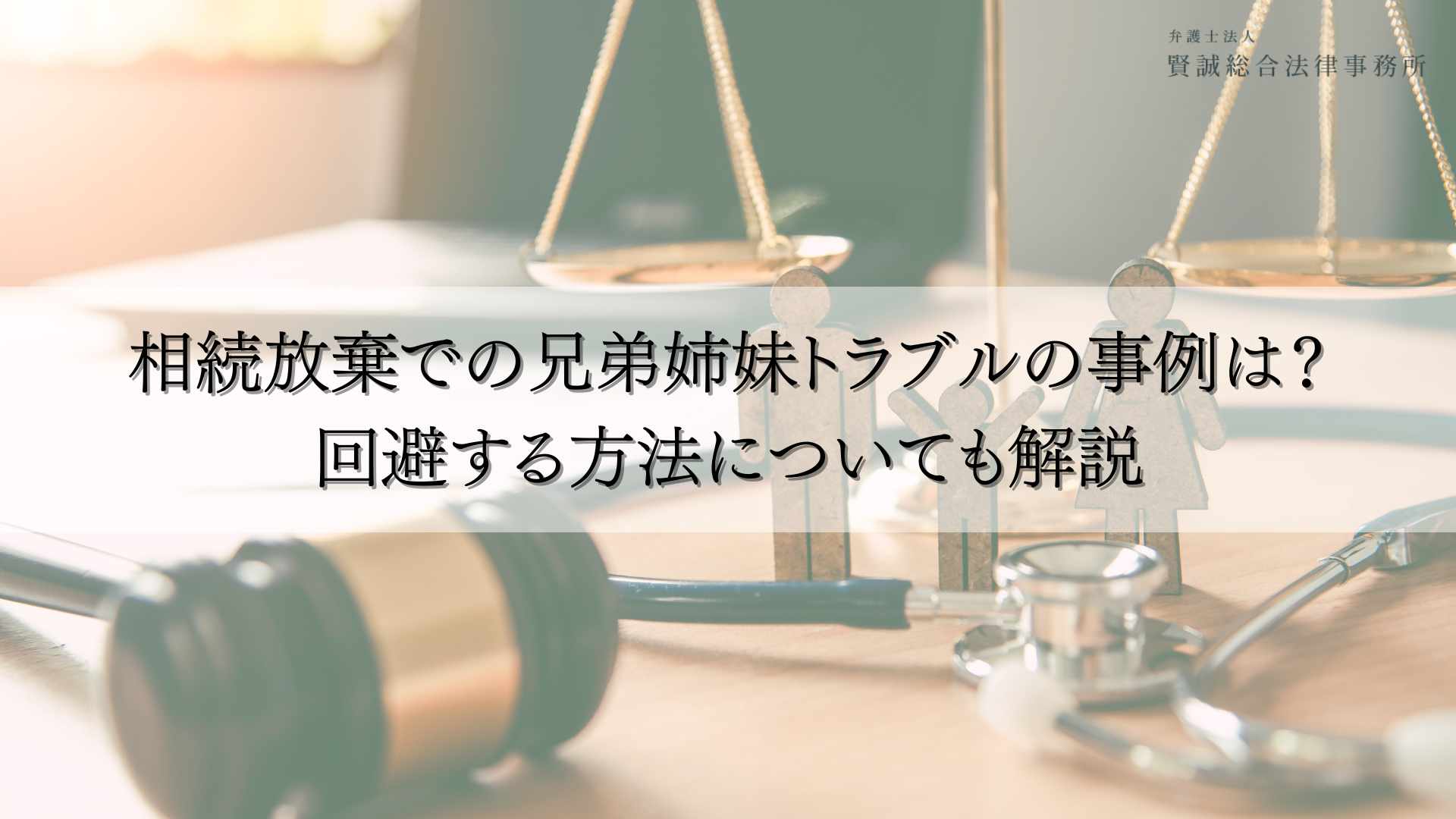
相続放棄の悩み
実績豊富な専門弁護士に
お任せしませんか?
- 6.6 万円/1人 ※追加費用無し
- 解決実績 2,500 件以上
-
全国対応
来所不要
「兄が勝手に相続放棄したせいで、私が借金を引き継ぐことになった」
「遺産は要らないと言っていたのに、後から保険金だけは受け取っていたらしい…」
相続放棄は本来「不要な遺産や借金を受け取らずに済むための救済措置」です。しかし、兄弟姉妹間で認識のズレや手続きへの誤解があると、感情的な対立や法的なトラブルに発展することも少なくありません。
この記事では、以下についてわかりやすく解説します。
- 相続放棄をきっかけに起こりがちな兄弟姉妹間のトラブル事例
- 放棄した側・されなかった側がそれぞれ抱えるリスク
- 後悔や争いを防ぐための具体的な対策
「できれば家族と揉めたくない」「損せず、安全に相続を終えたい」という方のために、相続放棄の基本から実践的なアドバイスまで丁寧に解説します。
1、相続をめぐる兄弟姉妹間でのトラブル発生事例
相続においては、兄弟姉妹との関係性や遺産内容によって深刻なトラブルに発展することも少なくありません。特に、被相続人との関係性に差がある場合や、相続財産に偏りがある場合には注意が必要です。
ここでは、相続をめぐって発生しやすい兄弟姉妹間のトラブル事例を5つご紹介します。
(1)兄が「すべての遺産を取得する」と主張する
遺産分割協議の場で、兄が「自分が長男だから」「面倒を見てきたから」といった理由で、すべての財産を取得するべきだと一方的に主張することがあります。
このような主張は、法定相続分の原則や他の相続人の権利を無視しており、当然ながら反発を招きます。遺言書がない限り、兄弟姉妹は原則として平等な相続権を持っており、勝手な主張は分割協議の決裂や関係悪化を招きかねません。
(2)兄が多額の生前贈与を受けていたのに、相続分を減らさないと主張する
「兄だけが親からマンション購入費や学費を出してもらっていた」といったケースでは、他の兄弟姉妹が不平等に感じ、「特別受益」として相続分の調整を求めることがあります。
一方、贈与を受けた兄側が「昔のことだ」と反論し、持ち戻しを拒否すると、法的・感情的な対立が起こりやすくなります。特別受益の有無は最終的には証拠(贈与契約書・振込記録など)で争われるため、客観的な証明がカギを握ります。
(3)葬式費用を遺産から控除すべきかで対立する
親の葬儀費用を一時的に兄弟のうち誰かが立て替えた場合、「その分を遺産から差し引いて分割すべきだ」と主張されることがあります。
しかし、他の兄弟姉妹からは「そんなに高い費用は必要なかった」「相談なく決められた」と反論され、協議がまとまらないこともあります。葬儀費用が妥当かどうか、領収書があるかどうかが争点となり、最悪の場合は法的紛争に発展するケースもあります。
(4)実家などの不動産の分割方法が決まらない
相続財産の中に不動産がある場合、それを「誰が取得するか」「どう分けるか」で揉めることが非常に多いです。
たとえば、「自分が住み続けたい」と主張する兄と「売って現金で分けたい」と主張する弟といった対立が起こりやすく、感情的な対立に発展しやすい部分です。
不動産は物理的に分けることができないため、共有・換価分割・代償分割など複雑な選択肢があり、弁護士などの専門家の仲介が必要になることも多々あります。
(5)誰が相続放棄すべきかで揉める
相続財産に債務(借金や滞納税金など)が含まれている場合、「放棄したい」と考える兄弟と、「放棄せずに最低限の財産を残したい」と考える兄弟とで意見が割れることがあります。
後で述べるように、相続放棄は自分一人で行うことができますが、このようなケースでは、放棄の前に全員で話し合い、必要があれば相続財産の内容を精査したうえで対応を決めることが、親族間のトラブルを防ぐうえで重要です。
相続放棄の不安、弁護士に丸ごとお任せしませんか?
初回相談無料/一律6.6万円(税込)※実費・債権者対応込み/全国対応・来所不要/実績2,500件以上。弁護士が完了まで代理対応、最短即日で催促ストップも可能です。
- 借金・滞納の請求が届いている/連絡を止めたい
- 3か月の期限が迫っている/過ぎてしまったかもしれない
- 書類作成や戸籍収集など手続きが不安・時間がない
- 家族全員で放棄したい/次順位の相続人への波及が心配
このようなお困りごとは、相続放棄に強い弁護士におまかせください。
2、兄弟姉妹のうち1人だけ相続放棄することは可能
相続放棄は「相続人一人ひとりの自由な意思」で行う手続きです。兄弟姉妹のうち誰か1人が単独で相続放棄することが可能であり、他の相続人の承諾は必要ありません。
ただし、放棄という行為は自分一人に関係するだけではなく、他の兄弟姉妹や次順位の相続人に直接的な影響を与えるため、事前にその結果をよく理解しておくことが重要です。
(1)兄弟姉妹のうち1人だけ相続放棄した際の影響
① 他の兄弟姉妹の相続割合が増加する
相続放棄をすると、その人は「初めから相続人ではなかった」と法律上みなされます。これにより、残された兄弟姉妹で相続財産を分けることになります。
たとえば、兄弟姉妹が3人いて1人が放棄した場合、残る2人で遺産を1/2ずつ分け合うことになり、相続割合が増えるわけです。
一見、財産が増えて得するように見えますが、以下のようなリスクもあります。
- 財産の中に負債(借金や滞納税)が含まれていた場合、負担が倍増する
- 放棄した人への不信感から家族間トラブルに発展することもある
相続放棄は、単なる個人の選択では済まない場合もあることを理解する必要があります。
② 相続放棄した本人は、相続税申告で死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が使えない
生命保険金や死亡退職金は、税法上「みなし相続財産」とされ、法定相続人1人あたり500万円まで非課税という特例があります。
しかし、相続放棄をした人は、法定相続人から外れるため、この非課税枠が使えなくなります。
つまり、保険金や退職金を受け取ったとしても、
- 税務上の控除が適用されず課税対象になる
- 結果的に税負担が重くなる
という事態になりかねません。
特に「借金があるから放棄する」という安易な判断は、保険金や現金資産の非課税枠の適用を逃すリスクがあるため、事前の財産調査と税務相談が不可欠です。
(2)兄弟姉妹全員が相続放棄した際の影響
① 次順位相続人(被相続人の兄弟姉妹など)へ相続権が移る、もしくは国庫に帰属する
被相続人の子らが兄弟姉妹全員で相続放棄した場合、相続権は次の順位へと移ります。多くのケースでは、被相続人の父母は既に亡くなっているケースが多いため、子の次に相続人となるのは被相続人の兄弟姉妹です。
そして、被相続人の兄弟姉妹も相続放棄をした場合、誰も相続しない状態になります。この場合は、裁判所により「相続財産清算人」が選任された後、最終的には、相続財産は国庫に帰属することとなります。
3、兄弟姉妹間での相続放棄トラブルを回避する方法
兄弟姉妹間の相続トラブルは、放棄の有無そのものよりも「情報共有の不十分さ」や「意思決定の一方通行」によって引き起こされることが大半です。
特に、放棄をする人としない人の間で事前のすり合わせがないまま進めてしまうと、「押し付けられた」「勝手に決められた」といった感情的対立が生まれやすくなります。
ここでは、相続放棄においてトラブルを避けるために重要な具体策を2つ紹介します。
(1)家族間で事前に意見を共有しておく
相続放棄は個人の権利である一方で、他の相続人に直接的な影響を与える行為でもあります。そのため、放棄を検討する段階で、家族間の情報共有と合意形成を行うことが最も重要です。
① 遺産内容や放棄の意向を共有し、書面で記録化しておくのがベスト
放棄の判断材料としては、以下のような情報を共有することが推奨されます。
- 相続財産の全体像(預貯金・不動産・借金・保険など)
- 相続人それぞれの考え方(放棄する・しないの意思)
- 次順位相続人への影響
話し合いの内容は、できればメモや覚書として書面化しておくと、後に「言った・言わない」のトラブルを防げます。
(2)専門家に相談し、適切な遺産分割をしてもらう
相続放棄に関する判断や手続きは、専門的な法律知識が必要です。特に、相続財産の中に不動産や借金、特別受益など扱いが難しい要素が含まれている場合には、弁護士などの専門家に相談することでトラブルを未然に防げます。
① 弁護士の関与で、適切な相続放棄書類や調整が可能になる
弁護士は以下のような点でサポート可能です。
- 相続放棄に必要な書類の作成と申述の手続き(3ヶ月以内の期限管理も含む)
- 遺産の内容調査と法的な評価
- 相続人間の利害調整と、トラブル回避に向けた解決策の提示
- 相続放棄後に発生する可能性のある管理責任や次順位相続への対処
特に、兄弟姉妹の間で意見が対立している場合、中立的な第三者である弁護士の存在は、感情を排して論点を整理する上でも有効です。
また、「放棄しても保険金はもらえる?」「相続税の非課税枠は?」といった誤解されやすい税制上の注意点も、弁護士や弁護士と連携する税理士から正しいアドバイスが得られます。
相続放棄の不安、弁護士に丸ごとお任せしませんか?
初回相談無料/一律6.6万円(税込)※実費・債権者対応込み/全国対応・来所不要/実績2,500件以上。弁護士が完了まで代理対応、最短即日で催促ストップも可能です。
4、兄弟姉妹の相続放棄に関するQ&A
相続放棄について、兄弟姉妹間でよく寄せられる質問にお答えします。
(1)全員が相続放棄した場合はどうなる?
相続人全員が相続放棄をすると、相続人が誰もいない状態になります。その後、利害関係人等による申立てにより、「相続財産管理人」が選任され、最終的には国のものになります。
相続放棄の相談は賢誠総合法律事務所へ
当事務所は、全国から多数の相続放棄の依頼を受けており、確かな実績を有しております。
熟慮期間を経過していたり、他の事務所で難しいと言われたりした場合でも、是非一度ご相談頂ければと存じます。
必要戸籍一式の取り寄せから、各案件に応じた申述書の作成、裁判所とのやり取り、最終的な受理まで、全て代理人である弁護士にお任せいただけます。また、被相続人の債権者への相続放棄の通知対応も致しますので、ご依頼者様の精神的なご負担も大幅に軽減されることと思います。
費用につきましては、全ての実費込みで、お一人当たり一律6万6000円(税込み)です。追加費用は頂きませんので、安心してご依頼頂けます。
相続放棄は是非、賢誠総合法律事務所にご相談ください。
まとめ
兄弟姉妹間の相続問題は、感情のもつれや誤解が原因で深刻化しがちです。相続放棄を検討している方は、早めに意思を共有し、必要であれば弁護士に相談しましょう。
第三者の立場からアドバイスを受けることで、誤解や不信感を最小限に抑え、円満な相続につなげることができます。
2025.07.16野田俊之
相続放棄の悩み
実績豊富な専門弁護士に
お任せしませんか?
- 6.6 万円/1人 ※追加費用無し
- 解決実績 2,500 件以上
-
全国対応
来所不要