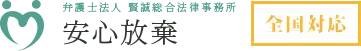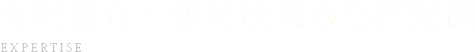熟慮期間中に相続人が亡くなった場合
相続放棄の悩み
実績豊富な専門弁護士に
お任せしませんか?
- 6.6 万円/1人 ※追加費用無し
- 解決実績 2,500 件以上
-
全国対応
来所不要
Aが死亡し、Bが相続人になったところ、BがAの相続放棄をするかどうかを検討している途中で3ヶ月の熟慮期間中に亡くなった場合、Bの相続人であるCは、Bが相続したAの相続人としての地位も承継するわけですが、このとき、Cが、Aの相続放棄をするかどうかを検討する熟慮期間の起算点はいつの時点になるのでしょうか。
民法916条は、「相続人(=B)が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人(=C)が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。」と定めております。ここでいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の解釈について、最高裁判所は、「相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人(=C)が、当該死亡した者(=B)が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。」と判示しました(最判令和元年8月9日民集73巻3号293頁)。
つまり、この場合の熟慮期間の起算点は、「CがBの相続人になったことを知った時」ではなく、「CがAの相続人としての地位を(Bから)相続により承継したことを知った時」となるということです。これにより、例えば、CがAとは疎遠な親族関係であり、Aが亡くなったことすら知らないような場合で、後からCがAの相続人としての地位も(Bから)承継しており、Aが多額の債務を抱えていたことを知った時でも、Cはその後3ヶ月以内にAの相続放棄の手続を行えば、Aの相続債務から解放されるということになります。
疎遠な親族からの相続では親族関係自体が複雑な場合も多いですので、お悩みの際はお気軽にご相談いただければと思います。
弁護士 相良 遼
2021.03.31相良遼
相続放棄の悩み
実績豊富な専門弁護士に
お任せしませんか?
- 6.6 万円/1人 ※追加費用無し
- 解決実績 2,500 件以上
-
全国対応
来所不要