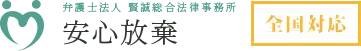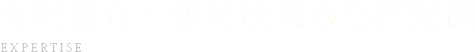相続放棄しても借金は消えず親戚中を追ってくる?借金が消えない理由と回避策を徹底解説
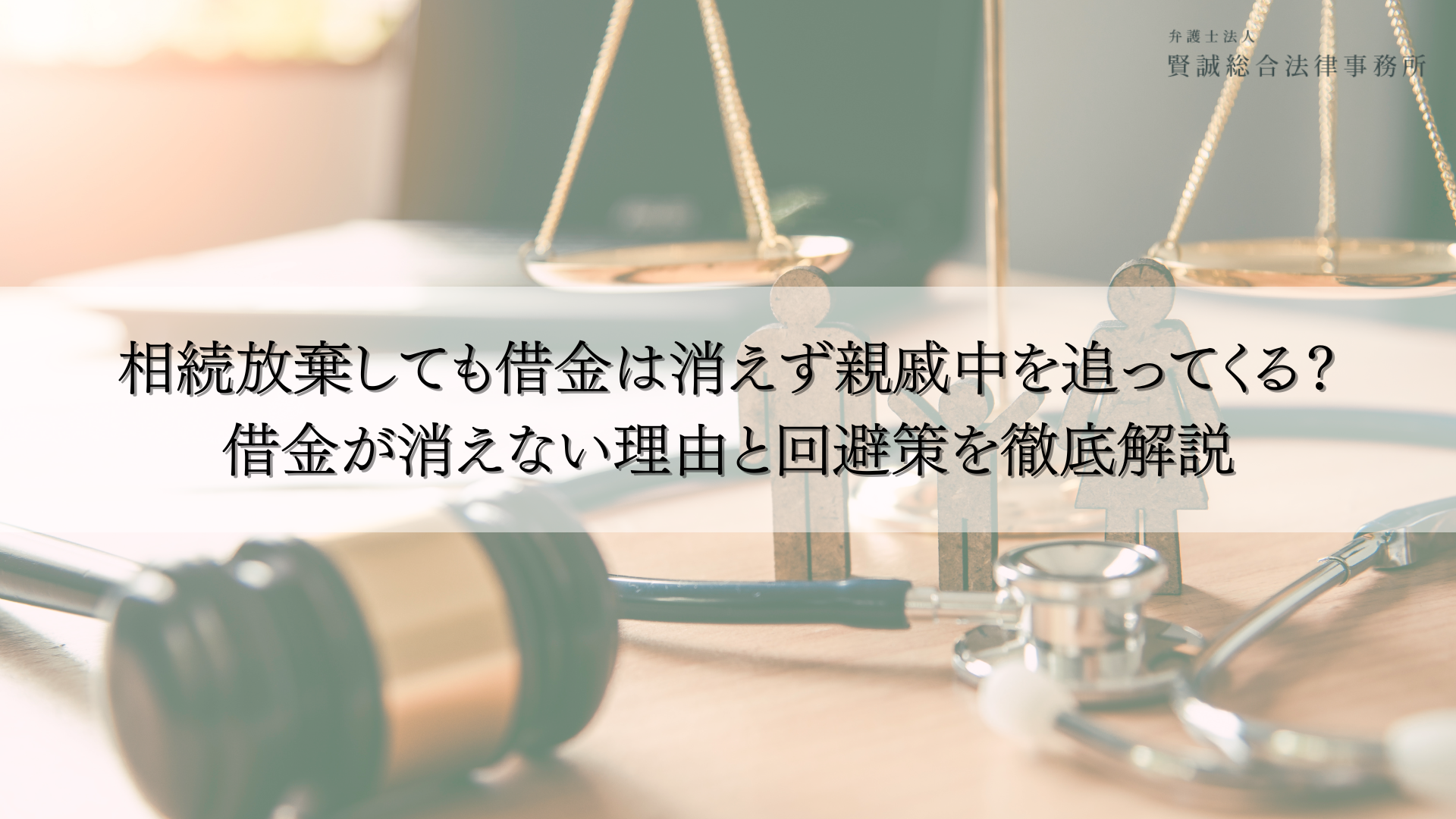
相続放棄の悩み
実績豊富な専門弁護士に
お任せしませんか?
- 6.6 万円/1人 ※追加費用無し
- 解決実績 2,500 件以上
-
全国対応
来所不要
「相続放棄をすれば、借金から解放される」と思っていませんか? 実は、相続放棄をしても借金の請求が“親戚中”に及ぶ可能性があることをご存じでしょうか。
相続の知識がないまま放棄を進めてしまうと、
- 借金の催促が止まらない
- 放棄したはずなのに保証人扱いされる
- 知らぬ間に親族トラブルが勃発する
といった深刻な問題に発展するケースが後を絶ちません。
本記事では、相続放棄しても借金が消えない理由や、借金問題を確実に回避するための具体策を、法律の専門知識と実例を交えてわかりやすく解説します。
1、相続放棄しても借金が追ってくる理由とは?
相続放棄をしても借金の請求が続くのはなぜか、不安に感じている方も多いでしょう。ここでは、相続放棄後も借金が消えない理由とその仕組みについて紹介します。
(1)相続放棄をすると次順位の相続人に責任が移る
相続放棄をしても、法定相続人が他にいる場合、その人に相続権が移る結果、借金の責任も移ります。
たとえば、子どもが放棄すれば、次は親、次に兄弟姉妹へと順番に請求がいきます。これを「相続順位」と呼び、債権者は、被相続人の相続関係に基づいて順次借金の請求を行っていきます。
つまり、相続関係によっては遠縁の親戚にまで借金の責任が及ぶ可能性があり、相続人本人だけでなく家族・親族全体の問題となるのです。
(2)放棄の事実を親族に知らせないとトラブルに
したがって、相続放棄したことを他の相続人に伝えなければ、次順位の人が相続人になったことに気づかず、突然、債権者からの請求書や督促状が届く可能性があります。
自分の相続放棄が確定したら、速やかに文書や口頭で他の相続人へ伝えることがトラブル回避の第一歩です。
相続放棄の不安、弁護士に丸ごとお任せしませんか?
初回相談無料/一律6.6万円(税込)※実費・債権者対応込み/全国対応・来所不要/実績2,500件以上。弁護士が完了まで代理対応、最短即日で催促ストップも可能です。
- 借金・滞納の請求が届いている/連絡を止めたい
- 3か月の期限が迫っている/過ぎてしまったかもしれない
- 書類作成や戸籍収集など手続きが不安・時間がない
- 家族全員で放棄したい/次順位の相続人への波及が心配
このようなお困りごとは、相続放棄に強い弁護士におまかせください。
2、相続放棄後に借金請求が来る典型ケース
相続放棄をしたはずなのに借金の督促状や電話が届くと、多くの人は驚きと不安に襲われます。ここでは、実際によくある相続放棄後の借金請求トラブルの具体的なケースを紹介します。
(1)連帯保証人だったケース
相続放棄をしていても、生前に被相続人の借金の「連帯保証人」になっていた場合、相続とは無関係に保証人としての返済責任が残ります。
「相続放棄すればすべての責任から解放される」というのはよくある誤解ですが、連帯保証人としての責任は相続制度とは全く別に契約に基づいて発生するものですので、被相続人が亡くなっても、その責任が無くなるわけではありません。
そのため、相続放棄をしても、契約に基づいて督促が届く可能性があります。督促が届いた段階になって「連帯保証人になったことを忘れていた」と気づく方も多いため、そもそも連帯保証契約を締結する際には、慎重に判断することが重要です。
(2)親族が相続放棄していなかったケース
相続放棄はあくまで個人単位の手続きであり、自分が放棄しても他の相続人が放棄していなければ、その人に借金の請求がいくのが通常です。
たとえば、自分が放棄したのに兄弟や親が放棄していなければ、債権者はその人たちに連絡を取ります。この流れは「相続順位」に基づいて進められるのが通常ですので、すべての相続人が相続放棄を完了しない限り、誰かが借金を背負うことになってしまいます。
(4)家族内で情報共有ができていなかったケース
誰が放棄したかを親族の中で共有していないと、「自分が相続人になっていることを債権者からの請求書で初めて知った」ということになりかねません。そうすると、借金の存在を全く知らされていなかった親族との関係性が悪化するなどのトラブルに発展しかねません。
こうしたトラブルを防ぐには、放棄したことを早めに親族に通知するのが理想です。相続は「自分だけの問題」ではないことを意識しましょう。
3、相続放棄の基本と注意点
ここでは、相続放棄を行う際の基本的なルールや、見落としがちな注意点について紹介します。
(1)相続放棄の期限は「3ヶ月以内」が原則
相続放棄には期限があり、原則として被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この3ヶ月間を「熟慮期間」と呼びます。
この期間中に、プラスの財産・マイナスの借金などを調査し、「相続するか、放棄するか、限定承認にするか」を決定しなければなりません。期間を過ぎると、自動的に相続を承認した(=単純承認)とみなされるため、慎重な判断と迅速な対応が求められます。
(2)借金が後から発覚した場合の救済措置
相続放棄の3ヶ月が過ぎた後に、実は被相続人に多額の借金があったことが判明することもあります。このような場合でも、条件を満たせば相続放棄が認められることがあります。
ポイントは、「いつ借金の存在を知ったのか」というタイミングです。死亡の事実は知っていたが、借金の存在を全く知らなかった場合、相続放棄をするに至った事情次第では、「熟慮期間の起算点が後ろ倒しになる(=借金の存在を知った時点がスタート)」と裁判所が認定する可能性があります。
その際には、債務の発覚時期や、相続人の行動履歴を証明できる資料(債権者からの請求書など)を準備しておくことが重要です。
(3)相続放棄が無効になる「単純承認」のリスク
相続放棄をしたつもりでも、ある行動によって「相続を受け入れた(=単純承認)」とみなされ、放棄が無効になるケースがあります。
たとえば以下のような行為です。
- 被相続人の預貯金を引き出して使う
- 借金を返済する
- 不動産を勝手に売却・賃貸する
これらは法的に「財産の処分」に該当し、これらの行動によって相続したとみなされるため、たとえ後から「放棄するつもりだった」と主張しても認められません。
(4)遺品整理や一時的な処分でも承認と見なされるケース
「遺品をとりあえず処分した」「家財をリサイクルに出した」といった些細な行為でも、法律上は「財産を処分した」と解釈される場合があります。
何気ない行動が単純承認とみなされたり放棄を無効にする可能性があるため、放棄手続きが完了するまでは、一切の財産に手を付けないのが基本方針です。
(5)限定承認の仕組みと相続放棄との違い
限定承認とは、「相続した財産の範囲内でのみ借金を返済する制度」で、相続人全員が一致して申述する必要があります。「プラスの財産もあるかもしれない」「借金の総額が不明で、完全に放棄するのはもったいない」と感じる場合に検討されます。
ただし、手続きが煩雑で、相続人全員の合意が必要、かつ不動産譲渡時に譲渡所得税が発生するなどのデメリットもあるため、注意が必要です。
(6)相続放棄と限定承認、どちらを選ぶべきかの判断基準
「放棄すべきか? 限定承認すべきか?」は、相続人の立場や家族構成、資産と借金のバランスなどによって異なります。
判断に迷う場合は、相続放棄の実績が豊富な弁護士に相談するのがベストです。弁護士は、相続人の関係性や財産・債務の状況を分析し、最も損のない選択肢を提示してくれます。
4、相続放棄後のトラブルを防ぐには?
相続放棄は個人の自由ですが、放棄したことを周囲に伝えないと、親族内で誤解や揉め事が発生する可能性があります。
ここでは、相続放棄によるトラブルを未然に防ぐための実践的な対策を紹介します。
(1)親族間での放棄連絡
相続放棄をした場合は、次順位の相続人に自分が放棄した事実を連絡するのが望ましいです。相続放棄が受理された日付や管轄の家庭裁判所・事件番号などを併せて連絡すると、次順位の相続人がスムーズに手続きを進めることができ、トラブル予防に効果的です。
放棄の事実を知らせなかったことで、次順位の親族が債権者からの請求書で初めて相続の開始を知るというケースは多いです。責任を押し付けられたと誤解されないためにも、放棄後は速やかに連絡を取ることが肝心です。
但し、先程述べた通り、相続放棄には熟慮期間という厳しい時間制限があり、この熟慮期間は、「自己のために相続の開始があったこと」を知った日から3ヶ月以内とされています。相続放棄をしたことを次順位の相続人に連絡する場合、この連絡の日が熟慮期間の起算点になりますので、この点は注意が必要です。
5、相続放棄で借金から確実に逃れる方法
ここでは、相続放棄によって借金問題から確実に逃れるための実践的な方法と専門家の活用術を紹介します。
(1)相続放棄は全体の見通しが重要
相続放棄は、法的には自分一人だけで完結することのできる制度ですが、実際には、「自分だけが手続きをすれば終わり」というわけではなく、他の相続人・親族人との関係性を考慮することが重要なケースもあります。自分が相続放棄をしたことが他の相続人へ影響を与えることから、親族間トラブルに発展するリスクを孕んでいるためです。
そのため、相続放棄をするにあたっては、まず、自分が相続放棄をした場合次は誰が相続権を取得するかなど被相続人の相続関係全体を把握した上で、相続人全員で相続放棄を行うのか・どの範囲で情報共有を行うのか、全体の見通しを立てることが重要です。
もちろん、どの程度他の相続人への配慮が必要かは、個々の家族構成や人間関係次第ですので、ご不安な方は専門家に相談することをおすすめします。
(2)弁護士への相談でリスクを大幅に軽減できる
相続放棄の手続きそのものは個人でも可能ですが、放棄後のトラブルを極力回避したい場合は、弁護士に相談するのが最善です。弁護士選びでは「相続放棄の実績が豊富」「相続全体を俯瞰して助言できる」点が重要です。
相続放棄の不安、弁護士に丸ごとお任せしませんか?
初回相談無料/一律6.6万円(税込)※実費・債権者対応込み/全国対応・来所不要/実績2,500件以上。弁護士が完了まで代理対応、最短即日で催促ストップも可能です。
6、よくある質問(FAQ)
ここでは、特に多く寄せられる疑問と回答をまとめました。
(1)相続放棄しても借金の催促が止まりません。無視してもいいですか?
無視は厳禁です。相続放棄の手続きを正しく済ませていても、債権者がそれを把握していない場合、催促が続くことがあります。その際は、家庭裁判所の受理証明書などを提示し、法的に放棄が成立していることを文書で通知しましょう。
(2)借金があることを知らず3ヶ月過ぎました。相続放棄できますか?
条件次第で可能な場合があります。「借金の存在を知らなかった」などの事情があれば、熟慮期間の起算日を「借金の存在を知った日」と認定してもらえる場合があります。ただし、個別事情によるため、被相続人の死亡を知ってから3カ月以上経過している場合には、速やかに弁護士へ相談することが重要です。
(3)親族から放棄通知が来ましたが、自分に責任が回ってきますか?
相続順位によっては可能性があります。前の順位の相続人が相続放棄した場合、次の順位にある親族に相続権が回ってきます。自身が相続人に該当するかを確認し、必要であれば放棄手続きを行うことで回避できます。
(4)相続放棄と限定承認、どちらが得ですか?
ケースバイケースですが、借金の額が不明なときは限定承認が有効です。限定承認なら、プラスの財産の範囲でしか借金を返済しなくてよいため、「もしかして財産もあるかも…」という場合には検討の価値があります。ただし、全相続人が共同で行う必要がある点に注意が必要です。
相続放棄の相談は賢誠総合法律事務所へ
当事務所は、全国から多数の相続放棄の依頼を受けており、確かな実績を有しております。
熟慮期間を経過していたり、他の事務所で難しいと言われたりした場合でも、是非一度ご相談頂ければと存じます。
必要戸籍一式の取り寄せから、各案件に応じた申述書の作成、裁判所とのやり取り、最終的な受理まで、全て代理人である弁護士にお任せいただけます。また、被相続人の債権者への相続放棄の通知対応も致しますので、ご依頼者様の精神的なご負担も大幅に軽減されることと思います。
費用につきましては、全ての実費込みで、お一人当たり一律6万6000円(税込み)です。追加費用は頂きませんので、安心してご依頼頂けるかと存じます。
相続放棄は是非、賢誠総合法律事務所にご相談ください。
まとめ
相続放棄をすれば、すべての責任から解放されると思いがちですが、実際には借金が次から次へと他の親族へ請求されることがあります。放棄を行った本人だけでなく、次順位の相続人にまで影響が及ぶことを正しく理解することが大切です。
借金トラブルを未然に防ぎ、親族間の関係を壊さずに安心して相続問題を処理するためには、戦略的な相続放棄が不可欠です。そのためには、自分で調べるだけでなく、相続放棄の実績が豊富な弁護士に相談することが、最も確実かつ安全な方法です。
相続放棄を正しく行い、あなた自身と大切な家族の未来を守るために、まずは専門家への相談から始めてみてはいかがでしょうか。
2025.07.01野田俊之
相続放棄の悩み
実績豊富な専門弁護士に
お任せしませんか?
- 6.6 万円/1人 ※追加費用無し
- 解決実績 2,500 件以上
-
全国対応
来所不要