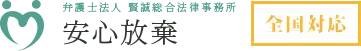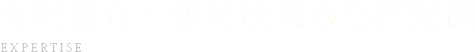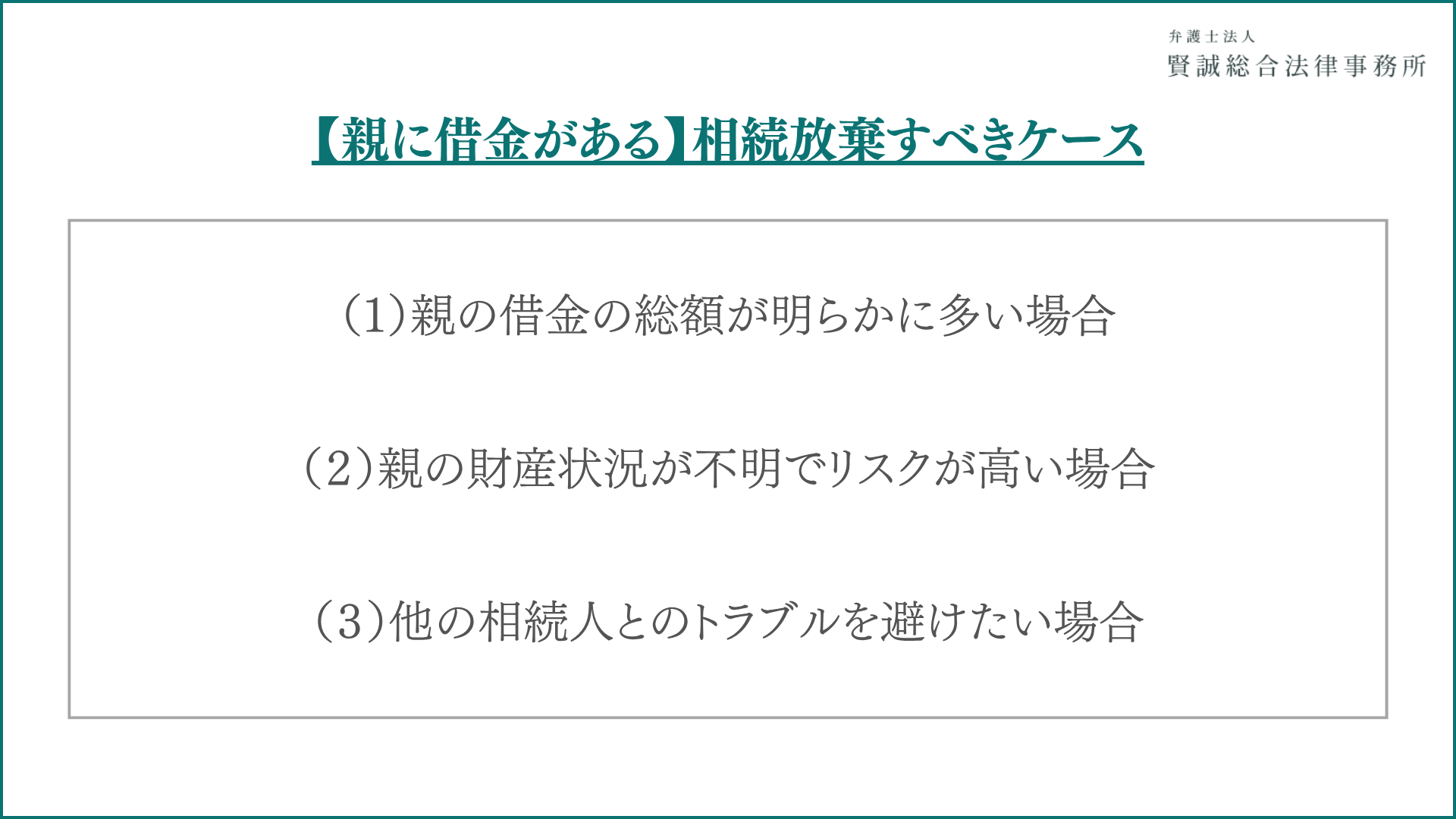親に借金があったら相続放棄すべき?専門家が教える正しい判断と手続き
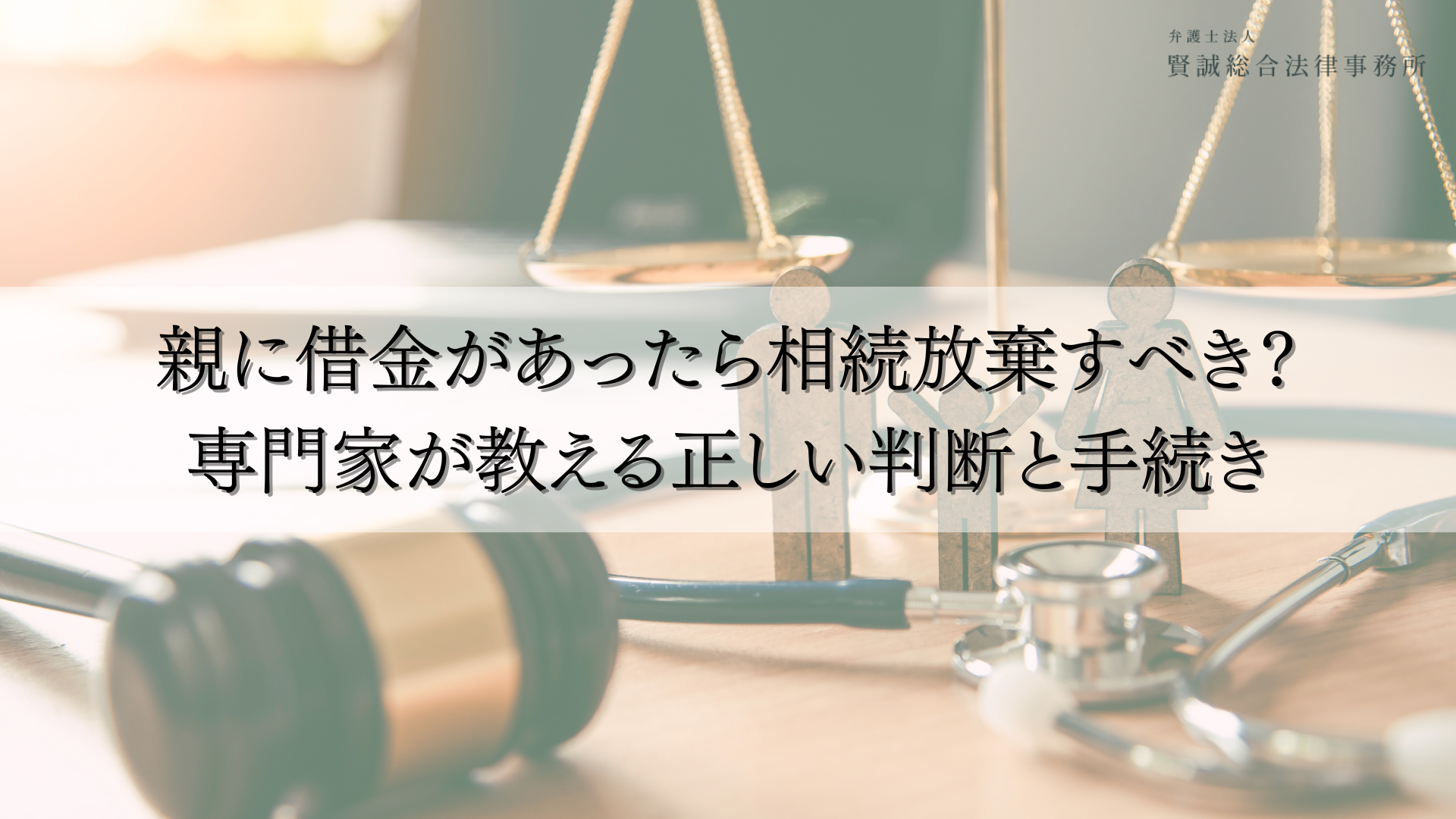
相続放棄の悩み
実績豊富な専門弁護士に
お任せしませんか?
- 6.6 万円/1人 ※追加費用無し
- 解決実績 2,500 件以上
-
全国対応
来所不要
親が亡くなった後に「実は借金があった」と判明したとき、子どもとして何をすべきでしょうか。
これは多くの人が直面する可能性のある問題です。親の借金は相続の対象になりますが、「相続放棄」という制度を利用することで、借金の負担から逃れることが可能です。
この記事では、相続放棄の基本から、手続き方法、よくある注意点、そして専門家に相談するメリットまでを弁護士目線で詳しく解説します。
1、相続放棄をすれば親の借金を相続せずに済む
親に多額の借金があった場合、それをそのまま引き継いでしまうと、自分の生活に大きな影響を及ぼしかねません。
ここでは相続放棄の基礎知識を紹介します。
(1)親の借金も相続の対象になる
① 包括承継とは何か?民法で定められた相続の基本ルール
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や権利義務を相続人がすべて受け継ぐ制度です。民法ではこれを「包括承継(ほうかつしょうけい)」と呼びます。財産(プラスの遺産)だけでなく、借金(マイナスの遺産)も含めて、原則としてすべてを引き継ぐことになります。
② 借金も自動的に相続される
親に消費者金融やカードローンなどの借金があった場合、相続人がそれを知らずに相続を進めてしまうと、プラスの財産だけでなくマイナスの財産もすべて引き継ぐことになるため、自分が返済義務を負うことになります。たとえ借用書や契約書を見ておらず、借金の存在を知らなくても、相続が発生すると法律上その義務が生じるため注意が必要です。
(2)相続放棄をすれば最初から相続人でなかったことになる
① 相続放棄とは何か?
相続放棄とは、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述することで、初めから相続人でなかったものとみなされる制度です。相続放棄が受理されると、財産も借金も一切相続しないことになります。
② 相続放棄は一人だけでも可能
自分一人だけ相続放棄を選ぶことは可能ですが、他の相続人に相続権が移る点にも注意が必要です。たとえば、子が放棄した場合、次の相続順位にある両親や兄弟姉妹が相続人となります。
自分が放棄することで他の相続人に借金の責任が移ることになるため、事前に親族間で話し合っておくのが望ましいでしょう。
相続放棄の不安、弁護士に丸ごとお任せしませんか?
初回相談無料/一律6.6万円(税込)※実費・債権者対応込み/全国対応・来所不要/実績2,500件以上。弁護士が完了まで代理対応、最短即日で催促ストップも可能です。
- 借金・滞納の請求が届いている/連絡を止めたい
- 3か月の期限が迫っている/過ぎてしまったかもしれない
- 書類作成や戸籍収集など手続きが不安・時間がない
- 家族全員で放棄したい/次順位の相続人への波及が心配
このようなお困りごとは、相続放棄に強い弁護士におまかせください。
2、相続放棄すべきケースとは?ケースごとの注意点も
相続放棄はすべての人が行うべきものではありません。しかし、一定の条件に当てはまる場合は、相続放棄を選ぶことで多額の借金を背負うリスクや家族間の深刻なトラブルを避けることができます。
ここでは、実際に相続放棄を検討すべき代表的なケースと、それぞれに伴う注意点を解説します。
(1)親の借金の総額が明らかに多い場合
① 負債が資産を大きく上回っているケース
たとえば「預金が100万円」「借金が500万円」のように、遺産全体がマイナスになることが明らかなケースでは、相続をすると損失を被るだけになります。こうした場合は、早めに相続放棄を行い、借金の相続を法的に回避するのが合理的です。
また、不動産などの資産があるように見えても、実際には担保付きローンなどで価値がマイナスになっていることもあるため、名義の確認だけで判断しないようにしましょう。
② 借金の種類に注意(保証債務・連帯保証など)
親が自分名義ではなく「他人の連帯保証人」になっていた場合でも、その保証債務は相続対象となります。保証債務は契約書を見つけないと把握しづらく、家族が知らないまま負担を引き継いでしまうことがよくあります。
(2)親の財産状況が不明でリスクが高い場合
① 相続財産の全容が把握できないケース
被相続人の財産状況が不明確なまま相続を進めると、あとから借金や滞納税金などが発覚することがあります。特に、被相続人が経営者だったり自営業をしていた方や、死亡後被相続人の通帳や契約書類を確認できないケースに多い傾向です。
このような場合は「相続放棄」または「限定承認(プラス財産の範囲でマイナスを返済)」を検討し、財産調査と同時並行で動くのが理想的です。
② 限定承認との比較も必要
限定承認は「プラスの財産の範囲内で負債を返済する」という制度で、完全に放棄はしないが損をしない仕組みです。しかし、相続人全員が一緒に行う必要があるため、他の相続人との連携が必須で、手続きも煩雑です。
家族の合意形成が難しい場合や、期限内に書類をそろえるのが困難なときは、相続放棄が現実的です。
(3)他の相続人とのトラブルを避けたい場合
① 兄弟姉妹との関係悪化を避けたいケース
相続では「誰が何を相続するか」で感情的な対立が起きがちです。特に借金のある相続では、「誰が負担するか」を巡って話し合いがこじれるケースが多くあります。
自分だけが放棄する場合、その分の責任を他の兄弟が負担することになります。事前に伝えておくと、関係悪化を避けやすくなります。
② 調整が難しいなら放棄が現実的
兄弟が多数いたり、関係が疎遠な場合、遺産分割のための協議が困難なこともあります。そういった状況では、自分が相続に関わらないよう「相続放棄」により関係性を断ち切ることも現実的な選択肢です。
3、相続放棄の手続き方法と期限は?
相続放棄は法的な効力を持つ正式な手続きであり、適切な時期と手順を踏まなければ無効となる可能性があります。
ここでは、実際に相続放棄を行うための基本的な流れと注意点について詳しく解説します。
(1)手続きの期限は『相続開始を知った日から3か月以内』
民法第915条により、相続放棄は「相続開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」といい、過ぎてしまうと原則として相続を承認した(単純承認)とみなされてしまいます。
親が亡くなった日が起算点とされるのが一般的ですが、死亡を知った日が遅れた場合、その「知った日」からカウントされます。戸籍の確認や通知の受領日など、客観的証拠を基に判断されるため、証明できる記録が重要です。
(2)相続放棄の申述に必要な書類一覧
相続放棄の申述に必要な書類は以下の通りです。
- 相続放棄申述書(裁判所の定型書式)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 申述人(相続人本人)の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 収入印紙800円と、郵便切手(裁判所によって異なる)
被相続人との関係性によって必要書類や切手の額に違いがあるため、申立先の家庭裁判所の公式サイトや電話で事前確認しましょう。
(3)手続きの具体的な流れ
相続放棄の手続きは以下の流れで行います。
- 必要書類の収集・準備
- 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出
- 裁判所から照会書が届く
- 内容に記入して返送
- 相続放棄の「受理通知書」が届く
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
相続放棄の手続き方法は?必要な書類や注意点について詳しく解説
4、相続放棄する前に知っておくべき注意点
相続放棄をすれば安心…と思われがちですが、実は注意すべきポイントや失敗例が数多くあります。
ここでは、相続放棄する前に知っておくべきことを紹介します。
(1)相続放棄後に財産へ手を出すと「単純承認」とみなされることがある
相続放棄をしても、親の財産を使用すると「相続を承認した(=単純承認)」とみなされる可能性があります。たとえば、以下のような行為はNGです。
- 親の通帳から預金を引き出す
- 相続財産を勝手に売却・処分する
- 遺品整理で貴重品を持ち帰る
ただし、不動産を雨漏りから守るなど、財産を保全するための行為(=保存行為)は認められます。線引きが難しいため、専門家に確認するのが安心です。
(2)保険金や葬祭費は相続財産に含まれないケースもある
生命保険に「受取人:長男○○」などと明示されている場合、その保険金は受取人固有の財産とされ、相続財産に含まれません。相続放棄していても受け取ることができます。
また、国民年金の遺族年金や健康保険の葬祭費も相続財産には該当せず、放棄後でも請求可能です。ただし、通帳の名義や引き出し方法によっては誤解を招くことがあるため、注意が必要です。
(3)相続放棄しても債権者から請求が届くことがある
相続放棄が家庭裁判所で受理されたとしても、債権者にその事実が通知されていない場合、請求書や督促状が届くことがあります。その場合は、「相続放棄受理通知書」のコピーを債権者に提示することで対応できます。
(4)一度した相続放棄は原則として取り消せない
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、原則として取り消すことはできません。「やっぱり不動産がほしかった」「プラスの財産が見つかった」という理由では認められません。
ただし、以下のようなケースでは例外的に取り消しが認められることがあります。
- 脅迫や詐欺によって相続放棄させられた
- 相続財産の存在について重大な誤解があった
いずれのケースでも、最後は裁判所の判断によりますので、専門家に相談することをおすすめします。
(5)放棄しても保証人義務が残る場合がある
相続放棄をしても、被相続人(親)の連帯保証人になっていた場合、その保証債務は「相続とは無関係」に個人の債務として残ることになります。
親の借金に関して保証人になっていないかどうか、契約書や借用書の確認が非常に重要です。不明な場合は、直接債権者に確認してみましょう。
相続放棄の不安、弁護士に丸ごとお任せしませんか?
初回相談無料/一律6.6万円(税込)※実費・債権者対応込み/全国対応・来所不要/実績2,500件以上。弁護士が完了まで代理対応、最短即日で催促ストップも可能です。
相続放棄の相談は賢誠総合法律事務所へ
当事務所は、全国から多数の相続放棄の依頼を受けており、確かな実績を有しております。
熟慮期間を経過していたり、他の事務所で難しいと言われたりした場合でも、是非一度ご相談頂ければと存じます。
必要戸籍一式の取り寄せから、各案件に応じた申述書の作成、裁判所とのやり取り、最終的な受理まで、全て代理人である弁護士にお任せいただけます。また、被相続人の債権者への相続放棄の通知対応も致しますので、ご依頼者様の精神的なご負担も大幅に軽減されることと思います。
費用につきましては、全ての実費込みで、お一人当たり一律6万6000円(税込み)です。追加費用は頂きませんので、安心してご依頼頂けるかと存じます。
相続放棄は是非、賢誠総合法律事務所にご相談ください。
まとめ
親が遺した借金も、原則として子どもが相続することになります。しかし、「相続放棄」という制度を正しく活用すれば、借金を引き継がずに済みます。
「何から始めればいいかわからない」「財産状況が不明」「兄弟と揉めたくない」といったお悩みがある方は、迷わず専門家に相談するのが最も安心です。
賢誠総合法律事務所では、相続放棄の相談・手続きサポートを多数扱っています。初回無料相談も実施中ですので、ぜひお気軽にご利用ください。
2025.07.01野田俊之
相続放棄の悩み
実績豊富な専門弁護士に
お任せしませんか?
- 6.6 万円/1人 ※追加費用無し
- 解決実績 2,500 件以上
-
全国対応
来所不要