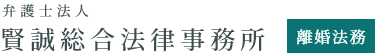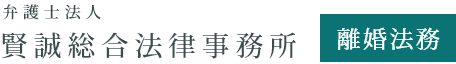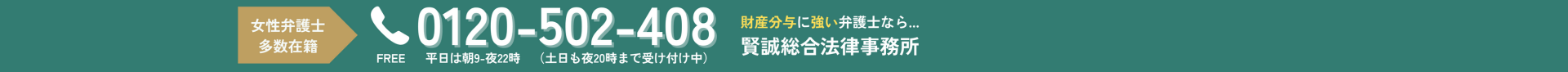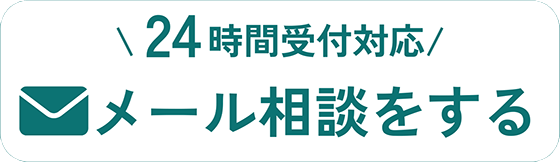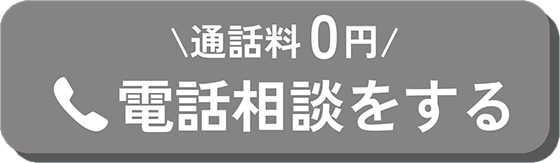普通預金を対象とする財産分与について
財産分与
1 はじめに
財産分与の対象は、夫婦が婚姻期間中に形成した共有財産となります。
しかしながら、預貯金については、原則、別居時の預貯金残高から婚姻時の預貯金残高が控除されず、別居時の預貯金残高全額を対象とすることが、一般的な判例実務となっております。これは、婚姻時の預貯金等が同居期間中に生活費等に充てられ、同居期間中の収入により填補されていた場合に、婚姻時の預貯金と渾然一体となるため、婚姻前から有していた預貯金の特有財産性について立証が困難となることを理由とします(詳しくはコラム「預貯金の特有財産性」をご参照ください)。
2 預貯金が特有財産と認められる場合
預貯金口座にて、婚姻以降、全く入出金がない場合には、婚姻時の預貯金残高(=別居時の預貯金残高)は、特有財産として財産分与の対象外となるでしょう。
さらに、相続や贈与により取得した財産は、夫婦によって形成された財産とは言えないため、特有財産にあたります。したがって、預貯金に相続した遺産や贈与金が含まれていることが立証できた場合には、遺産額や受贈額が特有財産として認められ、別居時の預貯金残高から遺産額や受贈額を控除した金額が、財産分与の対象となります。
3 大阪高等裁判所令和3年8月27日判決
被控訴人である妻が、妻名義の預貯金口座2つの残高全額が、ぞれぞれ妻の祖母の妻に対する贈与を原資とするものであると主張し、いずれも財産分与の対象とならないと主張した事案において下記のとおり、判示され、一部の預貯金の特有財産性が認められました。
「証拠及び弁論の全趣旨によれば、基準時における本件被控訴人預金3の残高401万2726円全額が被控訴人祖母の被控訴人に対する贈与を原資とするものであり、本件被控訴人預金4の残高314万1560円のうち約180万円(婚姻前に入金された額)は被控訴人祖母の被控訴人に対する贈与を原資とするものであることが認められる。これに対し、被控訴人は、同預金についても全額が特有財産であると主張するが、本件控訴人預金4のうち180万円を超える部分の原資については、本件の全証拠によってもこれを被控訴人祖母の被控訴人に対する贈与金であると認めるに足りない。
そうすると、本件被控訴人3の全額は被控訴人の特有財産と認められるから、同預金を財産分与対象財産から除外し、また、本件被控訴人預金4については、その原資のうち約180万円が被控訴人祖母からの贈与金によるものと認められるから、以上のような事情を考慮し、135万円の範囲で財産分与対象財産と認められるのが相当である。」
弁護士: 中川真緒