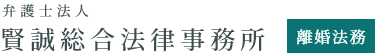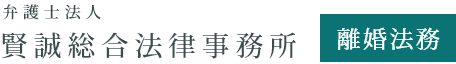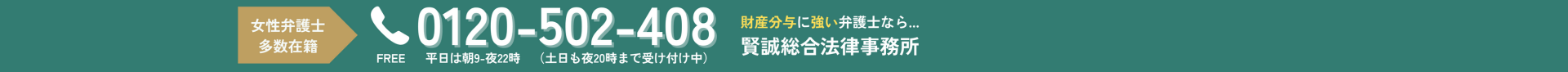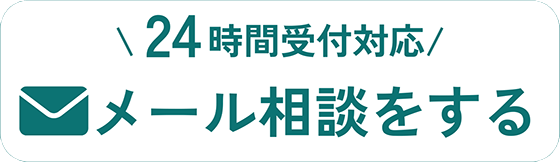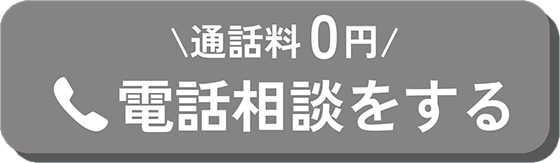有責配偶者からの離婚請求に関する、最高裁判例の分析
離婚
1 はじめに
有責配偶者から離婚請求については、最高裁判所が、①夫婦の別居期間が当事者の年齢や同居期間にてらし相当長期間に及ぶこと、②夫婦間に未成熟の子がいないこと、③相手方配偶者が、離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれるなど、離婚請求を容認することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が存在しないこと、等の事情を考慮して、有責配偶者の離婚が認められることもある、旨の判断をした(最判昭62年9月2日)以降、有責配偶者の離婚請求に関し、複数の判断を行っています。
本コラムでは、その後の最高裁判例についてご紹介いたします。
2 最高裁平成2年11月8日判決:離婚請求を棄却した原審を破棄・差戻をした事例
最高裁平成2年11月8日判決は、有責配偶者である夫からの離婚請求について離婚請求を棄却した原審に対し、離婚請求を「認めるべき」であるという方向で破棄差し戻しをしたものです。
判決文において、以下の通り述べられています。
『有責配偶者からの民法770条1項5号所定の事由により離婚請求の許否を判断する場合には、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んだかどうかを斟酌すべきものであるが、その趣旨は、別居後の時の経過とともに、当事者双方についての諸事情が変容し、これらのもつ社会的意味ないし社会的評価も変化することを免れないことから、右離婚請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たっては、時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮すべきであるとすることにある(最高裁昭和六一年(オ)第二六〇号同六二年九月二日大法廷判決・民集四一巻六号一四二三頁参照 )。したがって、別居期間が相当の長期間に及んだかを判断するに当たっては、別居期間と両当事者の年齢及び同居期間とを数量的に対比するのみでは足りず、右の点を考慮に入れるべきものであると解するのが相当である』とした。
つまり、最高裁は、別居期間が相当の長期間に及んだかの判断基準について、単に、別居期間と両当事者の年齢及び同居期間とを数量的に対比するだけではなく、当事者双方についての諸事情が変容し、これらのもち社会的意味ないし社会的評価も変化したかどうかをも考慮すべき、だと判断しました。
そして、最高裁は、以下の事由を考慮して、別居期間の経過に伴い当事者双方についての諸事情が変容し、これらのもつ社会的意味ないし社会的評価も変化したと窺われる、と判断しました。
・別居期間は約8年であるが、別居後においても、有責配偶者である夫は、妻及び子らに対する生活費を負担していたこと
・夫は別居後間もなく不貞相手との関係を解消したこと
・夫は離婚請求するについて妻に対し財産関係の清算について具体的で相応の誠意があると認められる提案をしていること
・妻は、夫との婚姻関係の継続を希望しているとしながら、別居から5年余を経たころに夫名義の不動産について処分禁止の仮処分を執行したこと
・成年に達した子らも離婚については婚姻当事者たる妻の意思に任せる意向であること
3 最高裁平成5年11月2日判決:離婚請求を認容した原審に対する上告を棄却した事例
最高裁平成5年11月2日判決は、原審の東京高裁平成3年7月16日判決において離婚請求が認容され、これを不服とした上告人が上告を行った結果、上告が棄却された事案です。
判決文において、『所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、夫婦関係の破綻について主たる責任は被上告人にあるが、上告人にも少なからざる責任があり、夫婦の別居期間が相当の長期間に及んでいて婚姻を継続し難い重大な事由があるとした原審の判断は、正当として是認することができる。』として、上告を棄却しました。
判決において考慮された具体的な事情は下記のとおりです。
・控訴審の口頭弁論終結時、夫は53歳、妻は54歳で、その婚姻期間は17年2か月の同居期間に対し、別居期間は9年8カ月に及んでいる.
・二人の子はともに成年に達していて未成熟子ではなく、離婚には反対していないこと。
・妻の不貞行為が婚姻関係の破綻を決定的なものとしたが、婚姻関係の破綻については夫による壮絶なDVなどがあった。
・妻の不貞行為は約2年間で終わっている。
夫による壮絶なDVについては、具体的には次の事情があります。
・夫は、41歳のときに勤務先を退職したが、退職について明確な理由はなく、その後の自らの進路及び一家の生活設計について何ら具体的な方針や見通しを持っておらず、これらの点について妻に説明や相談をしたり、妻の意見を聴いたりすることはなかった。
・夫は、終日家にいて徒食するという生活を送り、妻から就職するように再三求められても、聞き入れなかった他、勤務先の退職後、夫は全く生活費を負担せず、退職金は全て自らのために費消した。
・さらに、妻が仕事で多忙になり帰宅が深夜に及んだり、外泊したりすることもあったことから、夫は妻を責めて暴力を振るうようになり、夫は妻のベッドに水をまき、また深夜帰宅した妻に対してバケツに入った水をかけたこともあった。夫はその後、再就職をしたが、その後も全く生活費を負担することはなかった。
かかる判決において、別居期間だけではなく、不貞行為が短期に終わっていること、子が離婚に反対していないこと、そして有責配偶者である妻に対する夫のDVも勘案した上で、離婚請求が認められました。
4 最高裁平成元年3月28日判決:離婚請求を棄却した原審に対する上告を棄却した事例
最高裁平成2年11月8日判決は、有責配偶者である夫からの離婚請求を棄却した原審に対する上告を棄却しました。
その理由については、『別居期間が相当の長期間に及んでいるものということはできず、その他本件離婚請求を認容すべき特段の事情も見当たらないから』と述べています。
具体的な事情については下記のとおりです。
・夫婦の別居期間は、原審の口頭弁論終結時まで8年余り。
・夫婦の間には、4人の娘がおり、いずれも未成熟子ではない。
・離婚請求を認容すべき特段の事情がない。
以上のとおり、夫婦の別居期間が8年余りにも及んでおり、子がいずれも未成熟子ではないにもかかわらず、離婚請求を認容すべき特段の事情がないとして有責配偶者からの離婚請求を認めませんでした。
5 最後に
有責配偶者からの離婚請求については、別居期間のみならず、同居中の事情、別居期間中の事情、子が未成熟子であるか、子が離婚に反対しているかなど様々な事情を考慮して、判断されます。
当事務所では、有責配偶者からの離婚請求をされた方、有責配偶者に該当しうる方のご依頼を数多く受けておりますので、まずは一度ご相談ください。
弁護士: 中川真緒