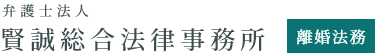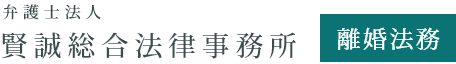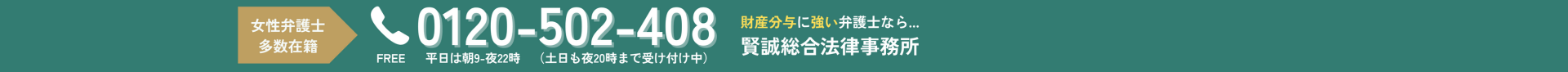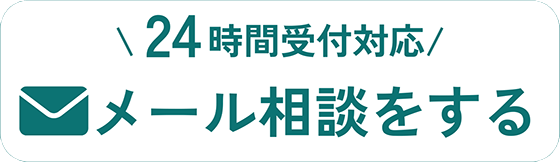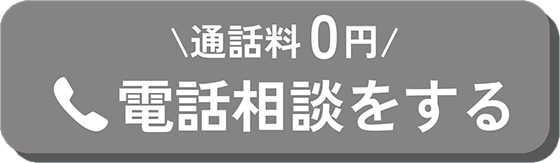有責配偶者からの離婚請求が認められる判断基準について
離婚の可否・不貞慰謝料等
- はじめに
有責配偶者(不貞等によって婚姻関係を自ら破綻させた配偶者)からの離婚請求は、かつては原則として認められていませんでしたが、現在の判例では、一定の要件を満たす場合には認められています。
このコラムでは、どのような場合に有責配偶者からの離婚請求が認められるかについてご説明します。
- 認められる要件
有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、主に次の3つの要件が考慮されます。
➀夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること
②夫婦の間に未成熟子が存在しないこと
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないことこれらの要件を満たす場合、有責配偶者からの離婚請求が信義誠実の原則に反しないとされ、離婚が認められるとされています(最大判昭和62年9月2日民集41巻6号1423頁)。
- その後の裁判例
しかし、近年は社会状況の変化に伴い、上記の要件を満たさなくても、一定の条件下で離婚が認める柔軟な判決が出てきています。
最判平成6年2月8日(集民171号417頁)では、別居期間が約13年、末子が17歳(高校2年生)という事案で、有責配偶者の夫からの離婚請求につき、夫が別居中に養育費を継続的に支払っており、離婚後の経済的支援も見込まれる状況にあったこと等から、「未成熟子の存在が本件請求の妨げになるということもできない」として、離婚請求を認めています。
また、東京高判平成26年6月12日(判時2237号47頁)では、婚姻期間約9年(うち同居期間約7年、別居期間約2年)、7歳と5歳の二子がある夫婦における、二子を連れた有責配偶者である妻からの夫に対する離婚請求という事案において、夫は安定した収入があり、離婚をしても経済的に著しく不利益な状態にはならないこと、妻は離婚後も子を養育する覚悟があり、子の福祉が害されるとは認められないこと等を理由に、離婚請求が認容されています。
一方で、裁判所が厳格に上記の要件を判断し、離婚請求を退ける例も依然として見られます。
東京高判平成元年5月11日(家月42巻6号25頁)では、夫婦の別居期間11年、17歳の子が一人、妻がパート収入と生活保護で子を養育しているという事案で、有責配偶者である夫が調停で決められた婚姻費用を2年しか支払わなかったことが特段の事情にあたるとして、夫からの離婚請求が棄却されています。
また、福岡高判平成16年8月26日(家月58巻1号91頁)では、夫婦の別居期間9年、未成熟子なしという事案で、有責配偶者の夫からの離婚請求につき、裁判所は、妻がパート収入と婚姻費用によってようなく生計を維持できている状態であること等から、信義誠実の原則に照らし容認されないとして、離婚請求を棄却しています。
- 終わりに
以上のように、有責配偶者からの離婚請求の可否は、個々の具体的な事情に応じて大きく異なります。
この点に関し、今後も、判例が蓄積されていくと考えられますので、お困りの際は弁護士にご相談ください。
弁護士: 長澤正高