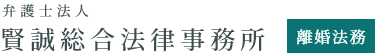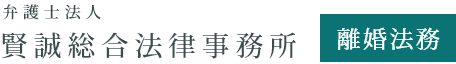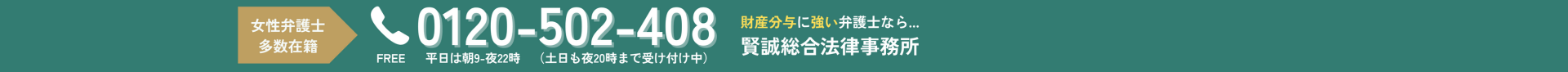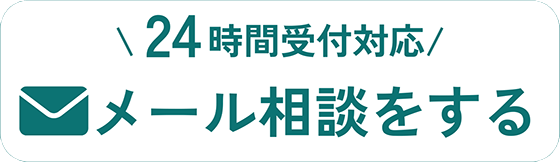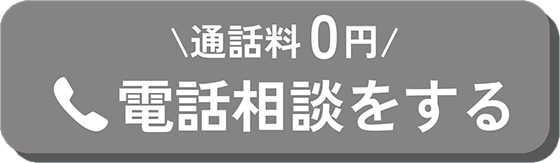未成熟子がいる場合でも有責配偶者からの離婚請求を認容した最高裁判例の紹介
離婚の可否・不貞慰謝料等
1.はじめに
前回のコラムで紹介した通り、昭和62年9月2日の大法廷判決(判例タイムズ642号73頁)は、有責者からの離婚請求について、①夫婦の相当長期間の別居、②未成熟子の不存在、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に苛酷な状態におかれるといった特段の事情の不存在の3つを、離婚請求が認められる三要件として示したものと解されてきました。
しかし、未成熟子がいるとされた場合でも有責配偶者からの離婚請求を認めた初めての最高裁判決として、平成6年2月8日の最高裁判決(判例タイムズ858号123頁)があります。本コラムでは、同判決の判断枠組みについて説明します。
2.本判決の判断枠組み
本判決において特徴的なのは、前述の大法廷判決の判断枠組みに従いながらも、その判断形式においては、厳密にはいわゆる三要件に即していない点です。
本件の事案としては、別居期間が約13年、末子が17歳(高校2年生)という事案で、有責配偶者の夫から妻に対して離婚請求がなされているという事案でした。
本判決では、まず、先の大法廷判決が、諸般の事情を考慮して信義誠実の原則に照らして離婚請求が容認されるかどうかを判断すべきであるとした部分を引用したうえで、未成熟子がいる場合でも、諸事情を総合的に考慮して離婚請求が信義誠実の原則に反するかどうかを判断すべきであるとしました。
そして、本件においては、高校二年生の末子は未成熟子であると認定した上で、三歳からずっと母親のもとで生育し離婚による環境の変化のないこと、高校を卒業する年齢であることから、未成熟子の存在が、離婚請求認容の妨げとはならないとして、離婚請求を認容しました。
本判決を嚆矢として、総合的判断により、未成熟子がいる場合でも、有責配偶者からの離婚請求を認める裁判例が現れるようになりました。
ただし、本判決は、未成熟子が山菜の時から現在の養育環境にあり、有責配偶者から妻に対する送金が継続的にされて子の養育責任も部分的に果たしてきたこと、子が間もなく親の看護を要しなくなることなどが考慮され、有責配偶者の責任や相手方配偶者の立場、別居期間等の事情と総合考慮した結果、離婚請求が認容された一つの事例判決です。
したがって、未成熟子がいる場合の有責配偶者からの離婚請求が認められることは、なお難しいものであることは間違いありません。
3.まとめ
以上のように、有責配偶者からの離婚請求の可否は、形式的な要件によって決まるのではなく、個々の具体的な事情に応じて大きく異なります。
この点に関し、今後も、判例が蓄積されていくと考えられますので、お困りの際は弁護士にご相談ください。
弁護士: 長澤正高