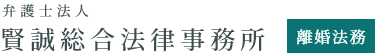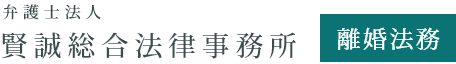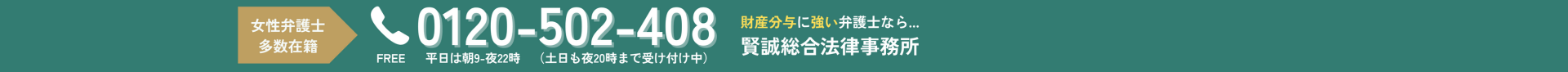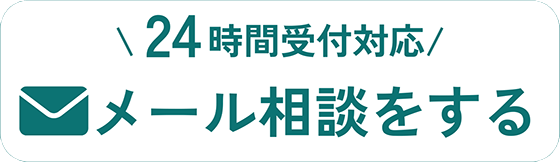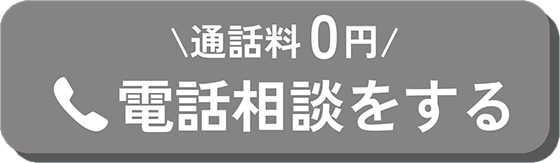財産分与における「2分の1ルール」が修正された事例の紹介
財産分与
はじめに
離婚に伴う財産分与における清算の割合は、「2分の1ルール」、すなわち、夫婦が協力して形成した財産に対する寄与度は、特段の事情がない限り平等と考え、2分の1の割合で清算するのが原則です。
しかし、寄与度の差が大きく、これを考慮しないと実質的に公平といえない場合、例外的に寄与度に応じた清算されるケースがあります。
本コラムでは、夫婦の財産形成に対する寄与度に差が認められ、「2分の1ルール」が修正された事例を紹介します。
夫が特有財産を原資に、経営者としての才覚で約220億円の資産を形成した事案(東京地方裁判所平成15年9月26日判決)
【2分の1ルールを修正した理由】
共有財産の原資のほとんどが、夫が婚姻前から保有していた株式などの特有財産であり、その後の資産増加も夫の才覚や経営努力によるものである一方で、妻の貢献は内助の功にとどまるとされ、財産形成につき夫の寄与が圧倒的に大きいと判断されました。
【認定された分与額】
共有財産の5%にあたる10億円を妻に分与
医師である夫が婚姻届出前の努力によって高額な収入の基礎となる特殊な技能を形成し、婚姻後もその才能や努力によって多額の財産が形成された事案(大阪高等裁判所平成26年3月13日判決)
【2分の1ルールが修正された理由】
夫が医師の資格を獲得するまでの勉学等について婚姻届出前から個人的な努力をしてきたことや、医師の資格を有し、婚姻後にこれを活用し多くの労力を費やして高額の収入を得ていることを考慮し、妻の協力を得る前の婚姻前の夫の努力が高額収入の基礎になっていると判断しました 。
【認定された寄与割合】
妻:夫=6:4
医師・医療法人経営者である夫の能力が資産形成の主因とされた事案(福岡高等裁判所昭和44年12月24日判決)
【2分の1ルールが修正された理由】
裁判所は、夫が多額の資産を築くことができたのは、妻の協力もさることながら、「夫の医師ないし病院経営者としての手腕、能力に負うところが大きい」と認定しました。
【認定された分与額】
裁判所は、婚姻期間や離婚に至った経緯、妻の医業への協力の程度など、様々な事情を総合的に考慮した結果、妻に対して金2000万円を分与するのが相当であると判断しました 。
一級海技士の夫が高収入を得ていた事案(大阪高等裁判所平成12年3月8日判決)
【2分の1ルールを修正した理由】
夫が国際的に通用する特殊な資格である一級海技士を活用し、長期間の海上勤務という不自由な生活に耐えて高額な給与を得た結果、財産形成がなされたと判断されました。妻は主に家庭を守り、家事や育児を一人で担っていたものの、高収入の源泉となった夫の特別な努力と能力が重視されました。
【認定された寄与割合】
妻:夫=3:7
童話作家の妻と画家の夫の事案(東京家庭裁判所平成6年5月31日審判)
【2分の1ルールを修正した理由】
夫婦がそれぞれ芸術家として独立して活動し、収入も各自で管理していました。その上で、妻が約18年間にわたり家事労働を全面的に担ってきたことや、双方の収入、生活費の負担割合などを総合的に考慮した結果、妻の寄与割合が夫を上回ると判断されました。
なお、各個人名義の預貯金や著作権については、それぞれの名義人に帰属する旨の合意があったと判断し、清算的財産分与の対象外としました 。
【認定された寄与割合】
妻:夫=6:4
妻が事業を築き、夫は遊興にふけっていた事案(松山地方裁判所西条支部昭和50年6月30日判決)
【2分の1ルールが修正された理由】
この夫婦が築いたプロパンガス販売業(営業権)などの財産について、裁判所は「主として妻の内職から始まり、妻が15年以上にわたり黙々と築き上げてきたもの」であり、妻の功労が非常に大きいと認定しました 。
その一方で、夫については「女狂いが多く、飲酒の上で妻に暴力を振るい、遊興にふけることが多く、資産の構築にはあまり努力が見られない」と指摘し、夫婦共有財産の形成につき夫の貢献度は極めて低いと判断されました 。
さらに、妻について、夫の暴力が原因で別居した後、独力で2人の子どもを大学に進学させるまで養育してきた経済的な努力も考慮されています。
【認定された寄与割合】
妻:夫=7:3
夫が婚姻前に購入した不動産のローン返済・維持に妻が尽力した事案(東京家庭裁判所平成23年4月26日判決)
【2分の1ルールを修正した理由】
夫が婚姻前に購入した不動産につき、原則として夫の特有財産とされましたが、①婚姻後、夫が十分な就労意欲を持たず働かない時期があっても、妻の貢献によってローンの返済が継続されたこと、②妻の尽力により金利の有利なローンへの借り換えが実現し、妻自身も連帯債務者になったことなどが財産の維持形成に寄与したとして、例外的に、この不動産の価値の50%を夫婦の共有財産とみなし、財産分与の対象とすることを認めました。
さらに、夫婦共有財産とみなされた「不動産の価値の50%部分」についても、財産を維持・形成した貢献度は妻の方が高いと評価されました。
【認定された寄与割合】
妻:夫=6:4
夫が小遣いを原資に購入した宝くじで約2億円が当選した事案(東京高等裁判所平成29年3月2日決定)
【2分の1ルールを修正した理由】
宝くじの購入資金は、夫婦の協力で得た収入の一部(夫の小遣い)から拠出された夫婦共有財産であると認定されました。しかし、夫自身がその小遣いの一部を充てて宝くじの購入を続け、偶然とはいえ当選金を取得し、これを原資にした財産形成は夫の寄与が大きいと判断されました。
【認定された寄与割合】
妻:夫=4:6
夫が小遣いを原資に購入した馬券が当たり、約1億9000万円の利益を得た事案(奈良家庭裁判所平成13年7月24日審判)
【2分の1ルールを修正した理由】
万馬券の利益は、射倖性の高い(偶然性の強い)臨時収入であり、その取得は夫の運によるところが大きく、これを原資にした財産形成は夫の寄与が大きいと判断されました。
【認定された寄与割合】
妻:夫=1:2
弁護士: 森 遼太郎