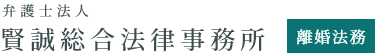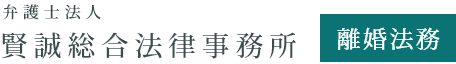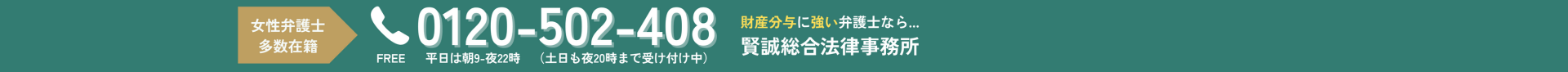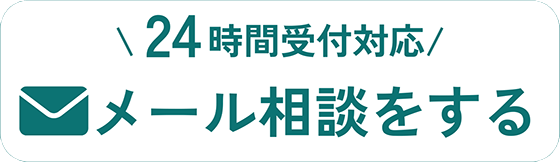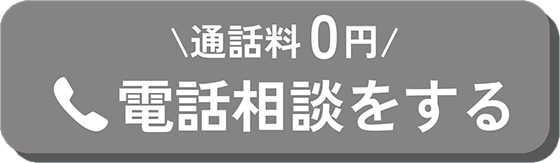退職金の財産分与
財産分与
1 はじめに
夫婦の一方が将来受給する予定の退職金は、離婚時の財産分与の対象となるのでしょうか。このコラムでは、将来の退職金が分与の対象になるかどうかについて考えていきたいと思います。
2 将来の退職金の財産分与について判断した裁判例
(1)分与の対象になるとした裁判例
ア 東京地判平成11年9月3日判時1700号78頁
この裁判例では、退職金には賃金の後払いとしての性格があることや、夫が取得する退職金には 妻が夫婦としての共同生活を営んでいた際の貢献が反映されているとみるべきであることから、退職金自体が清算的財産分与の対象となることは明かというべきであるとしたうえで、「将来退職金を受け取れる蓋然性(がいぜんせい)が高い場合には、将来受給するであろう退職金のうち、夫婦の婚姻期間に対応する分を算出し、これを現在の額に引き直したうえ、清算の対象とすることができると解すべきである。」と判示しました。
ここでいう「将来退職金を受け取れる蓋然性が高い場合」、つまり退職金が受け取れる確実性が高いかどうかが重要なポイントになります。
この裁判例の事案では、夫が6年後に定年退職予定で、また退職金の額も具体的に計算ができました。
このことから、①定年退職まであと数年であり、②退職給付金額が判明している場合には、「将来退職金を受け取れる高い蓋然性が高い」場合であるとして、分与の対象になると判断したと考えられます。
なお、分与の対象であることが認められるといっても、その受給額全額が対象ではなく、裁判例でも述べているとおり、婚姻期間に相応する期間に対応する金額が対象となります。
イ 東京地判平成13年4月10日戸籍791号9頁
そのほかにも、上記アの裁判例と同様に将来の退職金について分与の対象と認めた裁判例があります。この裁判例では、夫が13年後に定年退職予定という事案でした。裁判所は、夫が「北海道庁の地方公務員であり、退職予定時期が平成26年であって13年後のことではあるものの、民間企業と異なり、倒産等により退職金が受給できない可能性は皆無といってよく、何らかの事情で早期に退職することがあったとしても、その時までの勤務年数に対応した退職金を受給できることはほぼ間違いないと言える」として、将来退職金を受給できる蓋然性は極めて高い判断しました。
(2)分与の対象にならないとした裁判例
一方、将来の退職金は財産分与の対象にならないとする裁判例もあります。
たとえば、広島高判平成19年4月17日家月59巻11号162頁では、将来定年により受給 する退職金は、定年まで勤続することを前提として初めて受給できるものであるうえ、支給制限事由に該当すれば退職金を受給できず、また、退職の事由の如何によって受給できる退職手当の額には大きな差異があることから、現時点においてその存否及び内容が確定しているとは言えず、現存する積極財産として財産分与の対象とすることはできないとしています。
もっとも、この裁判例では、夫の勤続28年間の勤務について妻としての協力があったことは明らかであり、現時点で夫が自己都合により退職した場合でも退職手当を受給できると指摘し、夫が自己都合により退職した場合でも退職手当を受給できる地位にあることは、それを実際に受給できるのが将来の退職時ではあるものの、これを現存する積極財産として財産分与の対象とするのが相当であるとして、自己都合退職した場合の退職手当のうち婚姻関係に基づく同居期間に対応する額を分与の対象としました。
ほかにも、名古屋高判平成12年12月20日判例タ1095号233頁も、「将来の勤続を前提とし、しかも、その存否及び内容も不確定な控訴人の定年時の退職手当受給額を、現存する積極財産として、財産分与算定の基礎財産とすることはできない」としながらも、夫が妻と婚姻して別居するまでの間税務職員として勤務したことについて、「妻としての協力(いわゆる内助の功)」があったことを否定することはできないから、夫が現在自己都合により退職した場合でも、退職手当を受給できる地位にあることは、これを現存する積極財産として財産分与算定の基礎財産に加えるべきとしています。さらに、この裁判例では、自己都合退職した場合の退職金相当額と将来定年退職したときに受給できる退職金の実質的婚姻期間に対応する金額を比較した場合、前者の方が金額が少なくなるため、民法786条3項に定める「一切の事情」として考慮し増額を図っています。
3 まとめ
以上のとおり、裁判例では、①定年が数年後で、②退職金の額が判明している場合には財産分与の対象として認める傾向があるようです。
もっとも、近時の裁判例では、定年退職が相当先で将来の退職金が分与の対象とは認められない場合でも、離婚時に自己都合退職したと仮定して、その退職金を分与の対象とするものもあり、裁判所は事案ごとに細かな調整を図っているように見受けられます。
したがって、退職金が財産分与の対象になるかどうかは、それぞれのケースによって異なってきますので、退職金が財産分与の対象になるのかどうか容易に判断がつかない場合もあります。
そのような場合は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
以上
弁護士: 壽 彩子